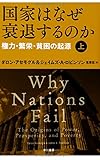
- 作者: ダロンアセモグル,ジェイムズ A ロビンソン,稲葉振一郎(解説),鬼澤忍
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2013/06/21
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (30件) を見る
ということで読み始めました。上下巻の本だし中身が濃そうなので、この出張中に全部読み終えるのはとても無理だろうと思って上巻しか持ってこなかったけれど、思ったよりサクサク読める。というのも、中身のほとんどは歴史的なエピソードで、しかもそのエピソードを細かく読み込まないと議論が理解できないというものではないから。
そして、そこで言われていることはきわめて単純。すなわち:
包括的で多元的な制度を持っている国は発展します。収奪的な制度のもとではダメです。
基本はこれだけ。
そして本書のほとんどは、「ここの経済はこんな具合に収奪的でした。だから発展しませんでした。」という話や「この国は一時は包括的で多元的で発達しました。でも既得権益が台頭して収奪的になりました。だからつぶれました」という話が何度も繰り返されることになる。
さて、これを読んでいる人の多くは(まだ本書を読んでいないだろうから)、わかったふりをしつつ実は包括的とか多元的とかいう意味がわかっていないはず。包括的というのは、その国のあらゆる人が決めごとに参加できる、ということ。多元的というのは、権力を持っている主体がいくつかあってそれなりに拮抗してチェック&バランスが働いている、とでも言おうか。
すると、「包括的で多元的な制度」というのは現在の世界環境では「民主主義」と言い換えていい。
が、そうなると本書の主張をものすごく乱暴にまとめると「民主主義国は発展します。独裁国/階級社会は停滞します」と言っているに等しい。さて、世の中そんな単純な話だろうか、と読んでいてぼくは首を傾げてしまう。
だってそれなら既得権益持っていた独裁者を爆撃したり拉致ったりしてぶっとばし、無理矢理民主化させて投票ごっこさせるというアメリカのいろんな活動は、結局いいってこと? もちろん結果的にダメなのはどこを見てもわかるけれど、そもそもの発想自体はいいってこと? ぼくはなかなかそうは思えないのだ。もう一つ、コリアー的な、民主主義はかえってアフリカ諸国には有害という議論をどう解釈すべきだろうか? ぼくは一理あると思うんだが、このアセモグル的な議論とは相容れるのかな。

- 作者: ポール・コリアー,甘糟智子
- 出版社/メーカー: 日経BP社
- 発売日: 2010/01/14
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 92回
- この商品を含むブログ (34件) を見る
さらにいまの世界は結構みんな民主主義してるけど、明らかに差が出ている。むろん、北朝鮮ですら建前は民主主義だ。中国も。でも実際にはあまり民主ってないのは周知のことだ……というとどちらの国も文句を言うだろうけれど。たぶんアセモグル&ロビンソンは、ここらへんの混乱を避けるために「民主主義ならよい」という言い方をしなかったんだとは思う。民主主義もあまりに様々だし。が、それは民主主義というものだけの話ではないんじゃないか。
つまり本書は、「包括的&多元的」というのや「収奪的」というのを、ほとんど1か0かのデジタルな概念であるかのように扱う。「ここが発展しなかったのは収奪的だったから」という具合。が、実際問題として、これって程度問題ですよね。完全に包括的で多元的というのはあり得ないし、完全に収奪的というのもない。相対的な問題だ。すると、どんな経済を見ても、失敗すれば収奪的だった部分をあげつらい、成功すれば包括的で多少なりとも少数派がおこぼれに預かっていた例を指摘できる。つまりこの議論は本当に何か説明できていると言えるのか? 岡目八目の後付アドホック議論でしかないとすら言えるのでは?
ついでに言うと、かれらは一方で発展の(特に初期には)むしろ強い中央集権が必要だと言ってるのね。すると発展段階があってうまく制度を途中で切り替えろってことになるんだろうか。
そしてもちろん、なぜそんな制度になったんですか/ならなかったんですか、というのは当然だれしも思うこと。それに対して著者たちは、ちょっとした違いと偶然、としか言えない。不思議なことに、この本はジャレド・ダイアモンドによる地理や自然環境的な議論を否定する。でも冒頭に出てくる北米植民者たち(その後の発展の基礎を作る制度を構築)と中南米植民者たち(収奪的制度を作る)の差を見ると、金が大量にでたかどうか、という自然条件が大きい。そしていったん制度ができてしまうと、それは数世紀たっても尾を引く。すると、ダイヤモンド的に、初期条件がすべてなのよ、と言うに等しいような部分もある。あるいはそこまで遡らなくても、たまたま近代化前の段階で絶対君主制でした、とかね。
そういう部分を読むと、ぼくは本書が「制度は変わらないのよ」という悲観的な本として理解されているのも、決して誤解とはいえないように思うのだ。いったんできた制度がそんなに尾を引いて変わらないなら、つまり制度って変わらないのであって、変われたところが例外なんじゃないの? 本書を読むと、本当にそんな印象が出てくる。あらゆる時代、あらゆる場所で、身内以外はとにかく収奪しまくれ、というのが基本の様式で、そうでなかったところというのはすさまじい偶然と微妙なバランスの産物以外の何物でもなかった、と。そして、アメリカによる爆撃強制民主主義はダメだ、とたぶん言うと思うんだけれど、すると人々が自発的に制度を変えるのを待てっつーことになりますわな。でもほっといたら過去の制度の遺産でいつまでも変わらないということも言ってますわな。すると、発泡ふさがりではありませんこと? 奇跡が降臨するのを待つしかないってことになっちゃうのでは?
また、上巻でのロシア革命の評価は、『トロツキー』他のロバート・サーヴィスの見解とはちがう。アセモグル&ロビンソンは、ロシア帝政は停滞していて、それを収奪的とはいえ社会主義が突破して一時的に発展させたと考える。サーヴィスはむしろ、帝政末期はむしろ改革と新規投資で発展がはじまっていて、その余剰をつかって革命が生じたと考える。ニワトリが先か卵が先か、というやつですな。どっちが正しいかはわからないが、本書の分析が必ずしも文句なしのものではないということは言えると思うのだ。
ということでここまでが上巻を読んだ感想。とても刺戟的で、いろいろ考えさせられるいい本なのはまちがいない。エピソードも、おもしろい。そしてもちろん、主張に一理あるのもまちがいない。でもやはり、この種の制度論について感じていた疑問はずっと残る。むしろ青木昌彦や新制度学派的な、制度もむしろ経済合理性から生えてくるのだ、という主張のほうがぼくは説得力あると思うんだが。その一方で、経済合理性の要請から経済制度がそんなにホイホイ変わるのであれば、なんですでにあらゆる経済はバシバシ発展するような制度になっていないんですか、というのも当然考えるべきことだと思う。
さて、こうした疑問が下巻に入るとすっぱり解消されるだろうか? 制度は変えられるのか、そのためには何が必要なのか――これに対してどういう処方箋が出てくるのか……これは日本に帰ってからのお楽しみになってしまうなあ。下巻も持ってくればよかった。
あと、これは索引は上下巻両方に同じモノがついているのかな? 一方で参考文献は下巻だけで……いろいろ苦心していて完璧とはいえないまでも、コスト上がってもいいから読者の便宜を優先するのは立派。
付記
あとこの本で言っていることって、結局はランデス『「強国」論』とかなり同じとは思う。(ちがったかも。ランデス読んだの物凄く前なのでかんちがいしてるかな? 帰国したら確認する)

- 作者: デビッド・S.ランデス,David S. Landes,竹中平蔵
- 出版社/メーカー: 三笠書房
- 発売日: 1999/12
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (4件) を見る

山形浩生の「経済のトリセツ」 by 山形浩生 Hiroo Yamagata is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 License.