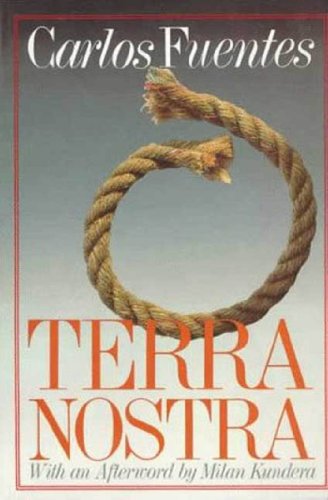やったー、昨日から100ページほど残していた部分完読! 読み終わったぜー!
最後の部分は、エル・セニョールの死……なんだが、そこになぜか、現代に生まれ変わったインディオの老婆としての旧女王(狂女)と、だれだかわからない人物との現代メキシコシティにおけるからみが入る。そのだれかが、南米の歴史をすべてその場で反芻し、無限の可能性があった新世界がキリスト教に支配され、アメリカ資本主義や共産主義に支配されるまでを体験したあと、アメリカの走狗としてメキシコを支配する兄を殺すところで場面はまた死にかけのエル・セニョールに戻る。
もはや財政的に破綻し、臣民たちに施しを求めるほどに貧窮しつつ、まだエル・エスコリアルにこもるエル・セニョール。最後に訪れたルドヴィコに、三人の私生児たちが実は無事だし、新世界に完璧な世界を創ろうという試みも破綻したことを知らされる。全身、痛みのあまり動かせなくなり、排泄物も垂れ流し状態で膿とウジに覆われ、最後の聖餐も拒絶されて死ぬ。
死後に霊となったエル・セニョールは、先祖たちの遺骨をおさめた 33 段の階段をのぼるが、そこで自分がこれまでの人生で行ってきた各種選択と、別の選択肢を(あまりに図式的な形で)示される。そしていつの間にか、かれは 1999 年にやってきて、神のために死んだ人々をまつるカイドスの谷にあらわれる。さらに、かつての自分の犬たちに狩られる狼となって――
そして最終章「最後の都市」へ。ここはカルロス・フエンテス十八番の、二人称で語られる。1999 年大晦日に、南米文学の主人公たちがパリに結集している(メンツは前回参照)。そしていかに南米が駄目になり、すべての希望が失われてしまったかを嘆きあう中、「お前」はうろつく。世界はもはや終末を迎え、疫病で人々は大量に死に絶え、経済格差と物質文明の中で貧困者や飢餓者が増大し、そして政府が市民を世界中で虐殺する中、「お前」はカーテンを閉じ、暗闇の中、同じ食べ物を食べつつ、己の世界と記録に閉ざされている。かれは過去の様々な存在で、明言はされないけれど、明らかにこの「お前」はエル・セニョールの生まれ変わりなのね。だがそこへ、真夜中の数分前にセレスティーナが訪ねてくる。そして「お前」が、冒頭に出てきた片腕のサンドイッチマンだというのがわかる。二人は性交し、そして二人は融合し、両性具有の存在となって、自分のチンコを自分のマンコに突っ込んでそれが子供を産み、孫を産み、人が無数に増え――
そして世紀の変わりを告げる鐘は鳴らない(ちなみに、20 世紀最後の年は 1999 年じゃなくて 2000 年だというのは、文中で冗談交じりに言及されているのでフエンテスもわかってはいる模様)。そして世界は続く。おしまい。
いやー、長かった。長かった!
全体を読み終えての感想
さて、読み終えてすぐの総合的な感想だ。
まず、力作。これはまちがいない。780ページもある化け物本について、他に何と言えるだろうか。そしてそこに込められた技法や作家としての力量もすごい。意外なイメージと、文学的、歴史的な言及の数々、時間とキャラクターの反復や融合の連続もすさまじく、これがそもそもまとまった小説になり得るというだけでも感嘆せざるを得ない。さらにそうした技法が、本全体のテーマともからみあう。そしてそのテーマとは?
本書のテーマとイメージ
それはもう、実に単純で、直線的な時間/進歩史観/固定的秩序と変化の拒否/二項対立/アメリカ資本主義やソ連共産主義はダメで、南米原住民とかの神話的な円環的時間/変化と多様性/三の豊穣といったものがいいんだ、というもの。単純ないい悪いではない、という言い逃れはできるだろうけれど、それが言い逃れ以上のものだとぼくは思わない。フエンテスは、こういう実におめでたく単純な図式を描いている。
第一部においては、エル・セニョールによるエル・エスコリアル城の建設が、スペインにおけるカトリックの一元支配の象徴となり、すべてを固定された何も変わらない秩序の世界構築への意志として描かれる。だがそれがもたらすのは、不毛と頽廃であり、エル・セニョール自身の異様な異端的思想だ。そして第二部で、すべてが反復し繰り返される神話的な新世界が描かれ、第三部で単一でない多様な場と可能性の渦巻く場所の可能性が描かれつつも崩れ去り――でも最終章で、単線的な世界のなれの果てが死と虐殺と貧困の中で滅びつつある中に、単線的な世界観の権化だったエル・セニョールの転生でもある「お前」(そしてこれはもちろん、読者でもある。サンドイッチマンは、本書の書かれた羊皮紙を読む人物でもあるのだから)と、そしてあらゆる時代に記憶を唇の入れ墨を引き継いで生き延びてきたセレスティーナが融合し、無限の豊穣さを獲得し、しかし時代の変化を告げる鐘は鳴らない――
しかし、今挙げたすべて――技法も重厚さもテーマも――が、本書の欠点でもある。まず何よりも、やたらに長いこと。特に第一部。旧世界のエル・エスコリアルの不毛を描くべく、本書はそのすべてを描こうとして、やたらに独白に頼る。ということはつまり、すべて説明調、ということだ。確かにその説明はうまいけど、でも長ったらしい説明は長ったらしい説明で、しかもその独白自体が多用されすぎて不自然となる。
そしてそれを廃そうとして、グロテスクなイメージと並置しようとする場合もあるけれど、それも決して成功はしていない。忠臣グズマンが、実は恨みをいだき叛乱の機会を狙っていることを明かす部分があって、グズマンは主人に薬を持って眠らせた上で、そのベッドの上で猟犬たちに性交させたりウンコをさせたり出産させたりして、その痴態醜態の中で主人に剣をつきつけつつ、10 ページにわたって独白を続ける。でもそれが鮮明なイメージとなることはなく、ウィリアム・バロウズの首つり乱痴気騒ぎ場面のように、絵の具の筆洗みたいなどろどろした単調さに陥るだけ。まさにその単調さを描きたかった、という言い方はあるけれど――そうではないと思う。一方で、言葉そのものの楽しさやだじゃれでやたらに言葉を重ねてしまうようなおもしろさもない。フエンテスはきわめてインテリであり、すべてを知的に構築している。でも、それがある意味でつまらないのだ。
フエンテス的歴史観の矛盾:進歩史観は変化しない??そんな馬鹿な。
そしてそれを使ってかれが述べようとしたテーマは説得力があるものなのだろうか? これは以前も書いたけれど、フエンテスの歴史観自体がそもそもこじつけがましく、矛盾しているのだ。
直線的な時間、キリスト教&アメリカ資本主義的な進歩史観というのをフエンテスは毛嫌いする。そして、この進歩史観というのが、すべてを単一の秩序におしこめ、あらゆる変化を圧殺するものなのだ、とフエンテスは言う。でも――進歩史観って、物事は変化する、というのが基本なんですけど? なぜ進歩史観が、変化を嫌い単一秩序にすべてを固定するという話になるの? 本書では、直線時間を求めるフェリペが、何も変わらない不動の秩序を求める存在となっている。でも時間が進むということはすべてが変わり、元には戻らないということだ。つまり、動かない秩序というものはないというのがその世界観となる。
そして円環的な時間は、すべてが繰り返される神話的な時間なんだって。でもすべてが円環し、何度も繰り返されるなら、すべては変わらないってことにならない? 実は、本当に動かない変わらぬ秩序を意味しているのは、円環構造の時間のほうかもしれないよ。
フエンテスはそこに逃げ口上を用意している。円環はまったく同じではなく、他の可能性もあるんだって。円環で戻ってきたとき、その別の可能性に移行する可能性もあるそうな。ふーん。でもその円環が少しずつ変わる(本書で主張されているように)ものなら、それはつまり、円環のように見えても実はらせん状に動いているといいうことだよね。つまりは、トポロジー的に言えば、それは直線時間の一種なんだよね。そして、実際に神話的時間に住んでいた人たちが多様性と変化を実現させていたかといえば、実際は停滞と単調さしかなかった。いや、その中に豊かさがあったかも、平凡な人生のよさもある、というかもしれないけれど、それって直線時間にもあったって構わないものだよね。
フエンテスの時間理解は、それ自体がこのように筋が通らない代物ではある。そしてラストで垂れ流される現代についての見方も鼻白む。直線的な時間は、ますます多くの貧困を作り出し、ますます多くの病気を創り出し、虐殺をもたらし、というのは実にありがちな、軽薄なインテリの、安手の現代文明否定だ。もちろん1970年代には、今よりもそうした主張が説得力を持ったのかもしれない。今だって、馬鹿なアームチェア評論家たちはすぐにこの手の話にはまる。でも――これ、全部まちがってますから。数字を見れば、そんなことになっていないのは明らかだから。
具体性のない観念だけの「新大陸」
さらにフエンテスは、メキシコの話をするときに、ヨーロッパ側からはスペインの実際の歴史をあれこれ持ち出す。これに対してアメリカ大陸側で出てくるのは、チャックモールとかケツアルクアトルとか、メキシコやインカの神様をやたらに持ち出して神話的な話をする。でも実際のメキシコに住んでいた人々について、具体的にはまったく出さない。かれは、ヨーロッパ文明と南米文明との融合や多様性みたいなことをあれこれ唱えつつ、実はアメリカ大陸側の人間なんかに何も興味を持っていない。単なる神話としての意匠に関心があるだけ。フエンテスは、そうした神話的な話とスペインによる実際の侵略とを組み合わせるのが新大陸と旧大陸の融合であるかのように主張する。でも、実はかれは、アメリカの原住民のことなんか何も考えていない。かれにとっての「新大陸」は、実は単なるオリエンタリズムにも似た観念でしかないのだ。これはフエンテスが後に『埋もれた鏡』で露骨に見せるようになった立場でもある。
そして、実はフエンテス自身が、自分の否定したのと同じ図式にはまっている。正しい秩序(つまりは円環的な神話時間)を求め、現代文明の破滅を願う――それはまさに、エル・セニョールことフェリペ2世がやろうとしたことだった。多様性とか融合ってそういうことじゃないでしょう。その両者が共存するということはできないの? 直線的な時間や進歩史観は否定されるしかないものなの? そしてそのフエンテスの望む方向に世界が進むのは、進歩じゃないの?
抽象化、観念化をはさもうとするフエンテス
さてもちろん、優れた小説は、別にその著者のイデオロギーに賛成する必要はない。ギュンター・グラスの思想や過去に賛同しなくても、その小説(少なくとも「ブリキの太鼓」と「ひらめ」は)すばらしい。でも、フエンテスの場合、そして特にこの小説の場合、そうはいかない。なぜか?
それはフエンテスの小説の作り方のせいだ。南米のマチスモ批判をしたい、というのは多くの作家が持っている考え方だ。が、それにあたり、マチスモ的な思想から生じた具体的な事件を描き、そしてそこから読者が自分で、その背景にあるマチスモに思いをはせる、という小説の作り方はある。
でも、フエンテスのこの小説はちがう。フエンテスはインテリだ。あることを描いたあとで、かれはそれをどうしても抽象化し、イデオロギー化し、そしてそのうえでそれを批判する。ガルシア=マルケスもインテリではある。でもかれは、ブエンディーア家の運命が何を意味しているか、などということを小説の中でわざわざ書かない。それは読者が自分で考えるべきことだ。でもフエンテスはちがう。少なくとも本書ではちがう。本書においても、時間のあり方、歴史のあり方、3の重要性、人間の複数性と多くの人々の重なりは、ものすごい饒舌性の中で、きちんと抽象化され、概念化されて説明される。読者としては、小説に書かれた具体的なものではなく、その思想や概念に対して反応せざるを得ない。だから、その思想や概念に説得力がなく、同感しにくければ、小説自体としての価値も下がってしまう。
これは非常に不思議なことだ。フエンテスの中編や短編は、そうした欠点を一切持たない。『アウラ』で、主人公がふと見るアウラとその祖母の共通の動作――それだけで、両者の同一性と時間の円環構造や人間の多重性は暗示される。本書で行ったような饒舌な説明はまったくなしに、読者はまったくちがう世界につれてこられ――そしてそれは小説の中でも、アウラと共に閉じ込められる逃げられない部屋として、この世からの隔絶として表現される。その完成度、そのちょっとした細部が醸し出す異様な豊かさ、そして読者に与えられた解釈の自由度――それは本当に驚異的なものだ。ところが長編だと、その魔法が消え去る。『空気澄み渡る所』は、初期の作品なので、饒舌なレトリックや露骨なイデオロギー主張は少なかった。その分おもしろかった。『アルテミオ・クルスの死』もまだいい。でも本書は、そうした技法を駆使しつつも――それが饒舌さに埋もれ、果てしなく続く独白にまぎれ、あまりにストレートかつナイーブなイデオロギーに押し潰される。
なぜだろうか。中編だとすべてに対して知的な目配りをするのが可能だけれど、これだけ長くなると、もはや全体を自分の脳内で把握しきれず、したがって文章そのものの力や流れ、比喩をすべてコントロールできないために、抽象度を上げざるを得ないから、なんだろうか。たぶんそんな気がする。本書は複雑そうに見えて、実は単純な話だったりする。それは、知的に構築する小説の限界、なのかもしれないとは思う。
そしてもう一つ。フエンテスはもちろん、本書でスペインだけの話をしたいわけではないんだろう。そして小説は、ある個別のことを書きながら、それが全人類にとって意味を持つ、という広がりが一つの醍醐味だ。マコンドで起こることは、マコンドだけの話ではない。それは全人類が共通に持つ悲劇だ。もちろん、そんなことを敢えて言ってもらう必要はない。そうした拡張や敷衍を読みながらできるかどうかが、小説を楽しめるかどうかを分ける。これはナボーコフであれば、感情移入という卑しい行為につながりかねないとして否定する考え方かもしれない。でも、そういう部分は絶対にある。
ところが本書においては、ぼくはスペインの外への広がりがあまり感じられなかった。もちろん、歴史観や円環的時間の反復、人々の重なりと蘇りにより、本書の話は時空を越えた広がりを持つはずだ――が、この小説を読んでそれが実感できる部分はきわめて少ない。それはまさに著者がしばしば「これはあらゆる時間に広がる」「ここに限った話ではない」と自分で言ってしまい、さらにはところどころアリバイ的に、ローマ時代の羊皮紙を登場させたり現代の話を入れてみたりするからなのだ。その意味で、本書は大部なのに/大部だからこそ、広がりに欠ける。第一部の、エル・エスコリアル城の閉鎖性と同じものが、小説全体を覆い、そこから解放される瞬間がほとんどない。
そして未来へ
これはまさに、ロバート・クーヴァーの書評の中で批判されていたことだ。クーヴァーは、本書自体が矛盾を抱えている、と指摘する。本書は、エル・エスコリアル城みたいな内にこもった構築的な志向を批判するものだ。しかし、780ページの小説というもの自体が、まさにそうした内にこもった自閉的な構築性を――作者にも読者にも――要求せざるを得ない。まさに、自分で自分の主張を否定するものになりかねないのだ、と。そして、それはその通りなのだ。
第一部を、今の半分くらいにしていれば、たぶんかなり本書は改善されただろう。最後の部分で、ティベリウス帝について書いたびんの中の羊皮紙は不要だったし、また現代メキシコと無理に続けようとする章も不要だった。そしてもちろん、本書にはすばらしい場面が多々登場する。新世界での神話的な探索、ルドヴィコの息子たちをつれた放浪、そして何よりも冒頭と、特に最後の章前半部分のかっこよさ(後半はとってつけたようでわざとらしいと思う)。でも――おそらくぼくは二度とこの本を読まないだろう。この本自体、プノンペンに置いてこよう。むろんフエンテスの理論によれば、これは終わりではない。ぼくはまた、他のところで、この小説の生まれ変わりを読むことだろう。ぼく自身が生まれ変わり、また『我らが大地』を読むこともあるかもしれない。が――無限の循環時間において、直線近似で得られるこのごく短い人生の直線においては――それもあと三〇年ほどしか残されていない直線時間では――ぼくは本書と二度と会うことはないように思う。一月くらいすると、少し意見もかわってくるだろうか?
本の裏の書店管理用シールを見ると、これを買ったのは2000年、まさに本書の話が終わり、新しい時代への希望が始まった年だったんだなあ。いや、そうなのかな? 1995年には買っていたような気もするんだけれど…… それから15年だか20年だかたって、やっと片付いたか。その意味では感慨深い。
他の意見
なお、本書については、成田瑞穂によるこんな解説もある。この人は、神戸市外語大学の人らしい。この pdf だけが転がっているので、いつ、どこに掲載されたものかはわからないけれど、pdf のプロパティからすると、2012 年の文のようだ。ぼくはほめすぎだと思う。小説に書いてあるというだけで、「よって歴史とはかくかくしかじかなものである」なんて言っていいのか? だがそれはもちろん人によって評価さまざまだろう。そしてもちろん、フエンテスの言う歴史や円環時間の解説についてはちゃんとしている。とっても参考になるし、読んでいる最中に迷子になったとき、あらすじを押さえるためだけでもどうぞ。
またもう一つ、フエンテス『我らが大地』に関するきわめて辛辣な記事の翻訳を載せているブログがあった。「ラテンアメリカ文学のブームの作家たちによる作品のなかでもっとも耐久性に欠ける作品」の第一位に、このフエンテス『我らが大地』が挙げられたというのだ。『我らが大地』は、もはやアナクロだ、という指摘がされたというわけだ。
その翻訳された記事は、辛辣な内容を書いた直後に、それを嘆いている。フエンテスがいかに優れた作家だったかを述べ、そして『我らが大地』に否定的だった投票者たちは、この本をちゃんと読んでいないだろうと言う。が、どうだろうか、ぼくは、読んだ人(そして読むための時間的投資に幻惑されない人々)こそまさに、本書のアナクロニズムを痛切に感じるはずだと思う。そしてそのブログの中には、もう一つおもしろいエピソードがある。フエンテスは『我らが大地』を読み切った読者がいるとがっかりしていたそうだ。かれは本書を、読めない本として構想していたんだって。
その記事は、それが何か刮目すべきことであるような持ち上げ方をしている。むろんこれが冗談であることを祈りたいところ。ぼくはこうした物言いは不健全で退廃的だと思う。そんなことをして喜ぶのは、衰弱したポモ的心性の発露だ。が、その一方で、フエンテスは知的でありすぎるがためにそうした面を確実に持っていた(『テルケル』にもてはやされるような部分ね)。小説の必然性として技巧を使うのではなく、技巧のための技巧、読者をおどかしうちまかすためにだけ技巧を使うようなところがあった。それがかれの小説の弱さ――特に本書の弱さ――の大きな原因ではあるように思う。

山形浩生の「経済のトリセツ」 by 山形浩生 Hiroo Yamagata is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 License.