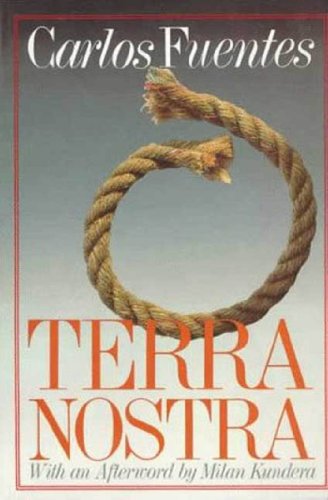さて第二部でも話はだんだん動きを持ち始めていたが、最後の部分になって、やっと話が本格的に動きを見せ、俄然読みやすくなる――とはいっても、相変わらず面倒にはちがいないんだが、第一部のような独白ばかりの鈍重さがなくて、しかもいろいろな伏線がつながり始めるので、読んでいて頭のバッファがクリアされていくのでホッとする。
第二部で、新世界の話をされたエル・セニョールは動揺する。自分はこの世の完成形としてエスコリアル修道院を構築してきたのに、いま知っているこの世以外の別の世界があっては、そのすべてが否定されてしまう、と。一方で、ドイツからなにやら本を増殖させる不思議な機械の話も伝わってくる。いままでは、えらい人がお金をかけてつくった写本だけが本で、それが正本であり、その持ち主がその「正しい」読み方を支配できたのに、いまやだれでも本を持て、本を読め、何が正しいかもわからず、唯一の正しい解釈もあり得ない、とエル・セニョールは嘆く。彼が嘆くその混乱は、実はエスコリアル修道院にある混乱と哄笑の巨大絵画にも現れていて、その絵を描いたのはヒエロニムス・ボスという人物のようだ。同時にその新世界にも神の福音を伝え、異教を根絶やしにして隷属させよという声が各方面から上がる。
そしてこれまでに登場した、六本指の足を持ち背中に赤い十字模様をつけた私生児三人の生い立ちもだんだん明かされる。それはすべて、先代のフェリペ王の落とし子で、それをエル・セニョールと共に一時反乱を率いたルドヴィコが育てあげていた。その三人はすべて同じであり、三人のうち二人が眠って夢見ることを3人目が実行するという奇妙な関係を保つ中、それがドン・ファンとなり、そしてドンファンがこんどはドン・キホーテとなり、様々な物語の中にいる自分を生き、やがて三人がばらばらになって、先代女王「狂女」とイギリスからのイザベルにそれぞれ拾われ、森からもたらされて、再びエスコリアル修道院で三人が集まる。子なしのフェリペ王は、その私生児の一人(ドン・ファン)を後継者にしようと考え始めるが――
そしてそこで、だんだん小説としての姿が見えてくる。時間はすべて円環的であり、歴史は常に繰り返す。人の可能性を全うするためには、人生一回では足りない。人は何度も生まれ変わる。先代フェリペ王は今のフェリペ王であり、そしてその私生児たちであり、父は息子であり、同じくフェリペと反乱軍を率いたセレスティナは幾度もその人格を引き継がれ、新世界でも私生児は記憶者でもあり「曇った鏡」でもある。人は鏡のように、自分と同じものを別のところに作ろうとし、そしてできたもの、鏡に映った己の姿に動揺する。フエンテスにとって、旧世界と新世界との関係はそうした曇った/歪んだ/埋もれた鏡。でも、その無限の(もちろん神話的な)繰り返しが続いても、それはまったく同じことの繰り返しではない。その円環を変えられる。少しずつ変えられる。
そしてそれを変えるのが、3という数字。1は自分だけ、2は対立と殺し合いにつながるだけ。3によりそれが融合され、対立がずらされて、多様性へとつながる。フェリペ、ルドヴィコ、セレスティーナがそうであったように。新世界で、生と死と記憶が同じ人物でありながら三種の存在であったように。旧女王の狂女と、現王妃イザベルと、セレスティーナがそうであるように。イザベルがイザベル女王でもありエリザベス女王でもあるように。私生児三人がそうであるように。スペインが、ムーア(イスラム)とユダヤ教とキリスト教の共存した唯一の土地(正直いって認識不足もはなはだしいけれど、フエンテスとしてはそう主張したいらしい)だったように。スペインの豊かな文化は、ドン・キホーテも含め、すべてそうした多様性の共存の産物だ。でも、キリスト教は――そして西洋文明は、と言いたいわけだ――3を否定して、すべて2の対立に還元してしまう。
ルドヴィコは、だから歴史を変えろ、とフェリペに言う。かつてフェリペは、ルドヴィコやセレスティーナとともに貧民反乱軍をエスコリアルに誘導し、虐殺させた。いま、また反乱軍がエスコリアルを取り巻いている。歴史が繰り返している。でもこんどはそれを受け入れろ、とルドヴィコは言う。かつてのスペインがそうであったように。そしてすべてが秩序だって固定された過去だけを見るネクロポリスとしてエスコリアルを作り上げるのではなく、かつてベネチアで見た記憶の装置のように、あらゆる組み合わせを可能にし、あったことだけでなく、あり得ること、あり得たこと、実際には起きなかったこと、そのすべてを現前させるものにしよう、と訴える。新世界もまたそういうものとして存在すべきなのだ、と。
だが、結局それは実現しない。フェリペはそれを拒み、三人の私生児たちはそれぞれフェリペ王たちの陰謀によって幽閉されてしまい、反乱軍はまた押し入っては虐殺され、フェリペ王側近のグズマンは新世界を征服するための遠征に乗り出す。フェリペ王は、ルドヴィコとセレスティーナを殺さず再び解放し、そして二人は一九九九年にパリの橋の上で出会おうと誓う。
そして――フェリペ王が半ば未完成の廃墟と化したエスコリアル宮殿の中をうろうろしているうちに、三人の私生児たちがかつて魔女の助言で海から引き揚げた、びんに入った羊皮紙を見つけてそれを読むと、カエサル時代のローマとそこでのナザレの男やピラトの話が延々書いてあるんだけれど、なんかこれはすごく場違い。フエンテスとしては、やたらにスペイン(とその鏡像たる新世界)の話ばかりしてるのはまずいと思い、歴史の反復がローマ時代から続いていたというのを強調したかったのかな? いまいちおさまりが悪い。
ということで、あと残すところ100ページ! やっとやっと最後までやってきました。あとはフェリペが死ぬところと、そして話がパリに戻ってさいごにまとまるところ。最終章の冒頭だけちょこっと見たけれど、話は小説冒頭のパリにもとってくる。パリを舞台にしたり、パリで創作されたりしたラテンアメリカ文学の主要作品からキャラが結集している模様。コロンビアのブエンディーア大佐(もちろん『百年の孤独』)。アルゼンチンの(『石蹴り遊び』)、唖のウンベルト(『夜のみだらな鳥』)、サンチャゴ・ザヴァリータ(『ラ・カテドラルでの対話』)、あとキューバ・ヴェネガスというのは知らなかったけれど、インファンテ『三匹の寂しい虎』なんだね。あといとこ同士のエステバンとソフィアって、何に出てくるんだっけ。(調べたらカルペンティエール『光の世紀』なんだね。読んでないや)がみんなパリに結集する。さてどうなるのか、話はつながるのか……
……と書いてはみたけれど、つながらないのはもうほぼ確実だ。本書が『埋められた鏡』で述べていた、非常に説得力のないテーゼをベースにしたものだというのはほぼ確実で。あとはフエンテスらしいスタイリッシュなかっこよさで終わってくれるかどうかが期待。おそらく明日には読了。終わって日本に持って帰るべきかなあ、どうしよう――というのは終わってから考えましょう。

山形浩生の「経済のトリセツ」 by 山形浩生 Hiroo Yamagata is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 License.