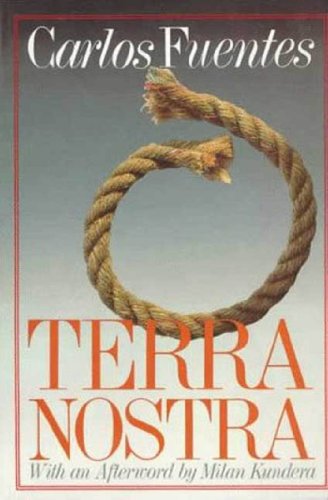さて一番短い第二部「新世界」は、六本指の私生児三人のうち、砂浜に投げ出されて発見した船乗りこと「巡礼」の語り。かれはスペインから新世界にでかけ、原住民につかまって、ハサミや鏡の交換によりジャングルの人々に受け入れられるが、やがて自分(生、ヨーロッパ人)と、自分の影(死、原住民)と、それをまとめる時間/記憶の交錯する中で神話的な旅に出て、他の自分を殺してはそれが蘇り、蝶の夫人に出会って愛を交わし、再会を約束して火山に向かい、メキシコシティに到着して再び己の三つの分身と神話的な対話を行い――というのが基本的なストーリー。
第一部に比べればはるかに読みやすく、またストーリーがあるのでおもしろいと言える。神話的な処理も非常に有効、ではあるんだが……
だんだんここで、フエンテスがやろうとしたことが明らかになってくる。フエンテスは『埋められた鏡』でやったみたいに、スペイン史とラテンアメリカ史/メキシコ史をごっちゃにしたようなものを構想はしている。ただし本書ではそれがあまりうまく融合できていない。フエンテスは、この両者をあわせたような一本の歴史みたいなものを考えているけれど、それをやるためには、どっかでスペイン人入植者たちによるメキシコの破壊と虐殺と収奪を扱わねばならない。
さてフエンテス自身はもちろん白人として、破壊収奪虐殺してきた側に近い存在なんだけれど、この融合した歴史みたいなことを言うためには、スペイン的なものと土着的なものがどっかでアウフヘーベンされたと主張しなければならないんだが――はっきり言って、そもそも現実においてアウフヘーベンされてないんだよねー。
だからこの新世界の部分はすべて、あまりおさまりがよくない。神話的な三位一体のイメージで、スペイン人と原住民とをくっつけようとして、虐殺その他は神話的に忘れ去られた断片的なエピソードとしてごまかされ、その同じことが円環的に繰り返されるのだ――そしてその体現者として「巡礼」がいるのだ、というレトリックでは、現実のメキシコやラテンアメリカに対する侵略史をとてもまとめ切れず、むしろ現実から目を背けるために神話をつかい、自分がそこに何か関係あるんだという妄想をつむいで同胞意識をかきたてるために、「新世界」を神話的にごまかしているように思う。『聖域』評での述べたけれど、フエンテス自身は、自分がそこにあまりうまく関係できていないことをうしろめたく思っている。何とかこじつけて、そこに関係をもちたい、歴史的に神話的にからめとられたいと思っている。でも本書くらいで、その試みがだんだん破綻してきたのを自分でも認識しはじめたんじゃないか。とはいえ、それを放棄したわけではなく、さらに晦渋になり苦しい理屈を編んでいっただけだとは思うんだけど。
むろん、第三部になってこれらすべてがうまーくまとまって、新旧世界が融合され、真の「我らが大地」が出現してきたらすごいんだが――あとは仕上げをごろうじろ。あと300ページ……
(続きはこちら)

山形浩生の「経済のトリセツ」 by 山形浩生 Hiroo Yamagata is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 3.0 非移植 License.