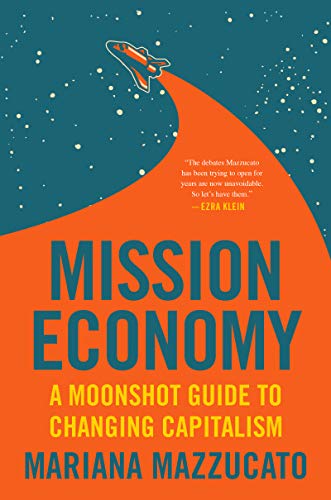2020年10月に依頼された、マリアナ・マッツカートの新著の査読。冒頭のコロナでの話とかでもわかるとおり、いまにして思えば (半年しかたっていないのに!) ずいぶん拙速で妥当性のない話になっているように思う。ベトナムなどは社会封鎖は成功したけれど、ワクチンとかは欧米のほうが対応がうまかった、ということになると、そもそものこの本の前提がいまや変だ。
読んだ時点でもピンとこなかったけど、まあ政府主導ででかいプロジェクトやってもいいんじゃね、とは思ったので、ぬるくはほめてある。彼女の強みは、ある意味でそのぬるさでもある。が、積極的にはすすめていない。
結局、出版社は見送りを決めたようで、正しい判断だったと思う。(付記:その後年末になって、見送っていなかったことが判明)
Executive Summary
コロナ対応の(欧米の) 混乱ぶりからわかるように、政府が弱体化して自分で何もできなくなっている状況は大きな混乱を招き、資本主義そのものの持続性にも関わる。民間は短期の目先の利潤にしか注目できず、長期の高い目標設定は不可能。公共の役割を再び強力にして、アポロ計画と同じように、経済や社会の目標を設定して民間の動きに方向性を与えねばならない!
この発想を元に、グリーンニューディールやデジタルデバイド解消など、政府が挙げるべき大きな目標をいくつか挙げし、その具体的な対応策を指摘する。
主張はきわめて単純明解であり、著者の前著での主張、つまりインターネットなども政府の投資の果実の結果であって民間はその尻馬に乗っただけ、というものを一歩進めたもの。まったく目からウロコではなく、80年代からの市場と民間盲信の振り子が逆にふれはじめた先鞭のような凡庸な議論だが、逆に世間的には理解されやすい。リベラル派政治家のブレーンとして活動しているのも理解できる。
著者について
マリアナ・マッツカートは、「企業家としての国家」で国が経済に果たす役割の重要性を指摘し、公共的なR&Dや投資が重要であることを指摘して有名となった。現在、ロンドンカレッジ大学で、イノベーションと公共価値についての経済学教授を務め、またイノベーションと公共目的研究所の創設所長。イギリス政府やアメリカの民主党リベラル派議員などのブレーンを務めている。
概要
第1章 本書のねらい
コロナ危機でも判るとおり、政府が主導権を取って対応したベトナムなどは押さえ込みに成功しているのに、なんでも民間に任せたがったイギリスや米国はひどいことになっている。民間や市場盲信をやめ、政府の役割を強化して新しい目標設定と市場の創造を行う必要がある。(付記:この議論は、初期の話。その後、初期の成功はすぐに新種株の増殖で台無しになり、さらに特にワクチン開発などにおいてこうした専制主義国家は遅れを取り、専制主義強権国家万歳という論調は即座に消えた。それと共に、本書の出発点が完全に崩れたことは認識しておくべき)
第2章 資本主義の危機
民間と市場盲信がここ40年続いてきたが、民間は近視眼的で目先の利潤しか見ない。一方、政府は常にtoo little too lateで、不十分なことを手遅れになってからしかできなくなっている。
第3章 ダメな理論とダメな実践:進歩を阻む五つの幻想
こうしたダメな状況は、民間が効率的で賢く、公共は常に鈍重で無能という通俗的な理論から逃れる必要がある。
第4章 アポロ計画の教訓
アポロ計画は、国がミッションを定めて主導権を取り、民間のイノベーションも主導した好例。それを振り返ることで今後の示唆を得る。
第5章 地上でのミッション志向政策
すでにSDGで、ミッションを定めて民間を動かすという活動は行われており、一定の成果を挙げている。もっと具体性の高い、グリーンニューディールやデジタルデバイド解消、万人にヘルスケアといったミッションは今後のミッションとして有望。
第6章 よい理論、よい実践:新しい政治経済学
民間と市場盲信、公共の蔑視から脱出。集合的な価値観のもと、役割分担をダイナミックに行い、長期的な資金提供と、多様な人々を包摂する新しい政治経済を構築する必要がある。
結論
政府と民間が力をあわせて新しいものをつくりあげる資本主義の新しい形が必要。
評価
主張はきわめて単純であり、また決して目新しいわけではない。特に中国の台頭もあって、政府がある程度の主導権を持って経済をリードすべきだ、という議論は比較的よく見かけるものとなっている。マッツカートもその一種ではある。80年代の市場と民間の過度の重視がいささか行きすぎた、という認識は特にリーマンショック/世界金融危機以来、ごく普通のものとなってきており、本書はそうした振り子の揺り戻しの一貫と言える。
本書の価値は、それがさほど過激でもなく、現在の社会的な認識の中でまあまあ受け入れられる程度の穏健なものとなっているところと、具体的に政府が定める目標/ミッションを描いて見せて、そのビジョンをある程度具体化しているところにあると考えられる。本書で挙げられたミッションが本当に著者の言うほど名案かどうかはわからない(検証もされておらず、思いつきの域を出ない)ものの、明解でわかりやすい。適度に政治的に正しいお題目も散りばめて世間的にも受け入れられ易く、英米政治家のブレーンとして重宝されているのもうなずける。
付記 (2021.12.23)
その後、結局邦訳を出すことにした模様。