Executive Summary
多くのものはいまや、価値が本来の機能ではなく、それ以外の本来の機能との差分/diffに宿るようになっている。酒はもともとアルコールの酩酊感のためのものだが、いまやアルコール以外の不純物がお酒の味の主役になっている。食事は栄養摂取が本来の機能だが、グルメ料理はそれを離れ、単なる舌や感覚への刺激だけを重視するようになっている。
今後、そうした部分が増えるのではないか。車もバイクも、「味わい」とされるのはニュートラルな移動機能から逸脱した歪み。いずれ、そうした部分だけソフトウェアなどで再現されてそれだけが分離されて取引され、その土台となるハード/本来の機能部分はコモディティ化してどんどん低価格化する世界がやってくるのではないか? ジャクソン・ポロックなどある種の芸術は、いちはやくそうした diff だけの世界を予見しているようでもある。
かなり前から考えていることがあるんだが、まとまりそうにないし、まあまとまってどうなるものでもないし、実証できるわけでもないし、抱えておいて何か出てくるとも思えないし、とりあえず吐き出してしまおうか。価値のありかた、みたいな話。それも希少性とかではない、ある種の主観的な価値の話。
価値の根拠というのは昔から謎で、特に実用価値からはずれた部分は面倒だ。実用価値、あるいは少なくとも何か計測できる既存の条件に対応した部分は、ヘドニックモデルを使って、どんな要素にどんな重みが置かれているかを回帰分析でもすればいい。不動産はかなりこの手が使えるので、楽と言えば楽。立地とか設備とか、絶対的な物理要素があるからね。でも、そうした物理的要素にあまり差がなくて、完全な思いこみの世界が増えてくると、なんか手に負えない。アダム・スミスも希少性で説明しつつ居心地悪い。だって希少だけれどまったく価値がないものなんて、腐るほどあるもの。どの希少性に価値があるのか? それはまったくわからない。マルクスも市場価値と製造原価との差みたいなものでウダウダした挙げ句、労働価値説みたいな話に流れて変なほうに流れて、話はうやむやになった。
で、いまの限界主義的な経済学だと、消費者余剰の概念持ち込んでそこらへんに折り合いをつけてはいるけれど、結局根本のところはわからん。消費者の効用関数を描くと、なんか知らないが鉛筆一本に100万円払っていいと思っている、頭のおかしい変な消費者が一人くらいいたりすることになっている。その変な消費者は何を考えているかは、追求しないことになっている。
でも、多くの価値というのは本当に、その物理的な本質と離れた部分に宿るようになっている。それは無形資産とかブランド価値とかいうもの以上の話ではある。
たとえば酒、というものがある。で、みんなこの酒はいい、あのワインは神の雫で乙女がペガサスにのって振り返って〜みたいなことを言う。
でもご存じの通り (って、知ってるよね?)、アルコールというのは味がない。純粋エタノールは無色透明。だから人びとが酒について語る、甘いとか辛いとか、深みがあるとか平板とか、うまいとかマズいというのはすべて、アルコールとは関係ない。純粋アルコールに入った不純物についての議論であるわけだ。ぼくのある友人はドイツ人のくせに「ビールなんかクズだ、ウォッカの純粋アルコール体験が〜」と語っていた。でもそいつも、本当に純粋なエタノールを飲んでいたわけではない。
酒の持っていた、純粋に酔うためというアルコールに依存した機能がある。そしてお酒の本来の機能的な本質はそこにある。だからこそ酒税はアルコールに対してかかる。
でもいまや、お酒の持つ価値というのはその本来の機能的な本質から完全に離れたところにある。お酒が醸造や蒸留の過程で取り除けない (あるいは時には追加さえする) 不純物の部分に価値が宿っている。人がありがたがるお酒の価値は、すべて不純物に存在する。ワインだろうと、ウィスキーだろうと、日本酒だろうと。
(厳密に言えば、アルコールには味をまとめる力があるため、そうした不純物の味わいを成立させるためにアルコールが要る、という主張はありえるが、まあそこは見逃せや)
そして、いまや人はその不純物だけを分離してありがたがり始めている。ノンアルコール・ビールという代物は、お酒のアルコールを除いた不純物だけを飲んでいるものだ。不純物でないアルコールに価値があったのは、人びとが貧しくて、つらさを忘れるために手っ取り早く酔いたかったからだ。でも、その部分はもう化学的にいくらでも合成できるようになった。そしてその部分に価値を抱くのは、間もなくある種の病人とみなされるようになるだろう。喫煙者がいまや貶められているように。そしてそのとき、人はやがて、ノンアルコール・ワインとか、ノンアルコール・ウィスキーとか、ノンアルコール・ウォッカとかノンアルコール焼酎といったものを作り出すようになるんじゃないか。(注:すでにあるって。)
たぶん喫煙者でも似たような話が起きつつあったんだとは思う。タバコはニコチンによる酩酊感が当初の本質ではあった。それが紙巻きタバコで普及して広まり……でもそれが電子タバコに移り始めたところで禁煙運動が強化されたのか、あるいは禁煙運動があったからこそそうした移行が起きたのかはわからない。煙が少なくてニコチンも (ある程度) 限られる代物が普及し、いずれはニコチンはニコチンパッチで供給されて、でも別の刺激を求めてノンニコチン電子タバコ的なものだけが残る世界もあったのかもしれない。禁煙排撃運動の高まりが急速すぎて、それが定着する暇がなかったようなのは、まあ残念といえば残念ではある。
ここにあるのは、何かその活動が持っていた機能的な本質——その活動そのものを成立させて延命させてきた、言わば実体的な価値——から、その活動の持つ価値の中心が離れつつあるという現象だ。そうした活動の中心は、ますます人工的に合成できるようになっている。あるいはそれだけ分離するのがますます容易になっている。それが、その活動の、言わば「零度」だ。この使い方が正しいか調べようとして、わざわざロラン・バルト『零度のエクリチュール』読んだけど、倒れそうなバカだったわ。だから無視して、こういうものをその活動の零度だということにする。それが合成できるようになるにつれてますます希少性は下がり、価値は低下していずれ限界価値は零になる——その活動の価値の中心でありながらほとんど無価値、という部分だ。
そしてかつて、その活動の価値はその零度の部分にあったのが、いまや価値はその零度の部分との差分、つまりdiffに宿るようになっている。酒飲みにとってすら、中心的な価値はアルコールにあるのではなく、差分、diffに宿る。タバコの価値も、ニコチンとはちがう部分で成立するようになる。
こうした、物事の価値がその機能的な中心部ではなく、その中心部からのズレ、diffに宿るようになる現象は、ますます増えるんだろうと思う。それはもちろん、機能的な中心部分はますます合成できるし、機械化し自動化できて、それだけ価値が低下するからだ。あらゆる活動の価値は、その「本質」からの逸脱に宿るようになるだろう、とすら言えるのかもしれない。
これは当然、各種の表現活動ですでに顕著に出てきた。これは写真が出てきたときの絵画の問題でもあり、スマホで写真が大衆化したときの写真の課題でもある。物事の姿を映像としてそのまま描き出す、という絵画の持っていた機能は完全に写真に奪われた。そのとき、絵画の価値はどこに残るだろうか。
あるいは、もはや小説が現実の記録手段としての役割を終えたら? ディケンズやある種の写実主義、リアリズム的な文学、つまりは第一種の小説とアンソニー・バージェスが呼んだものの価値が、他の記録メディアの発達に伴って激減した。そのとき、文学の価値はどこに残るだろうか?
それはやはり、その差分だ。絵画においては、やがて写実的な描き方からの逸脱を誇張するような形で発達が起こった。それこそキュビズムだし、ジャクソン・ポロックだのイヴ・クラインだのが出てきたわけだ。小説においては、アンソニー・バージェスが第二種小説と呼ぶような、リアリズム表現から果てしなく逸脱した、言葉遊びなどのナボコフであるとか、ウィリアム・バロウズであるとかが登場した。

音楽はどうだろう。すでに楽譜通りにそのままきっちり演奏するだけなら、機械のほうがいい。「Our music is sampled, totally fake/ It's done by machines 'cause they don't make mistakes!」。それが音楽にとっての零度、とは言える。
が、音楽の価値——少なくともある演奏の価値——というのはそこにはない。その零度からどんなふうにずれるか、というところに味わいがあるし、演奏家の個性や工夫も出る。
一部の料理もそうだ。一部では世界最高のレストランとも言われていた、エル・ブリなるところがある。そのお仲間のようなモレキュラーなんとかいうのが一部は流行っている。どんなものか知りたければ、下の映画でも見て欲しい。匂いのついた紙のに匂いを嗅ぎながら、油を垂らした水をすする——あるいは何かお椀の中に封じ込めた香料を湯気といっしょに吸い込んで喜ぶ——そんなのが彼らの「料理」だ。
結局これって、食べ物から栄養価、生存のために必要な要素を除去して、それと料理の差分だけを残す、という「食」のあり方だ。ここでは、人間の持つ各種のセンサーを刺激する方法だけが考えられている。生存手段としての食べ物、栄養摂取手段としての (お望みならレヴィ=ストロース的な文化的意味づけを加えてもいい) 料理、つまり本当は「食べる」という行為が持っていた実用的な本質は消え去っている。その消え去った部分との差分だけがここにある。
バイクでもいい。人びとがバイクについて語る価値——低回転の力強さが云々とか、高回転でのピーキーな挙動が、とか、コーナリングがオーバーステア気味なのを抑えつつ乗りこなすのが楽しいとか——は、すべてあるニュートラルな走りからのズレのことだ。先日、久々に教習所通いをして乗った、バイクの教習車として使われるCB400は本当に信じられないくらい素直なバイクで (だから教習車に使われるんだけれど)、アクセル開いただけスッと加速し、こちらが意図した通りに曲がり、ピタリと止まる。無理してデカいバイクに乗っていた人がCB400に乗って、その扱いやすさにため息を漏らすのをときどき見かける。ぼくはそんなにバイクに乗っているわけではないけれど、それでもある意味で、最もフラットでニュートラルなバイクのあり方だろうと思う。

でも人びとが価値を置いているのは、まさにそうしたニュートラルな走り方からのズレだ。無音で完全にスムーズな、純粋移動手段的なバイク像がなんとなく念頭にあり、それに比べて急発進するとか加速がもたつくとか、いきなり高回転でトルクが不連続に上がるとか、ブレーキの効きがギクシャクするとか。ホント、みんな何をハーレーなんかありがたがっているんだい、とぼくは思う。でも知っている人ならご存じの通り、CB400とかは「面白みがない」とか「優等生的」とか言われてしまうことも多い。いずれ電動バイクは、CB400さえも凌駕するだろう。いまの電動バイクは、アクセル開いた時の急発進ぶりに課題あるけど、いずれそれもソフトで如何様にも調整できるはず。たぶん、それは「面白みがない」と言われることになるだろう。
そしておそらくは、そこからずらすための様々な電動バイクのソフト的なセッティングが出てくるだろう。それがその「バイク」の「価値」となるのかもしれない。バイクの走る部分とは離れて、カスタムバイクの世界の中に、電動バイクのセッティングだけのソフトウェアとしてのバイク、みたいなものが、案外大きな市場として登場してくるかもしれない。
ということで、いろんな「価値」は、その中心的、本質的な機能との差分、プログラマーならご存じのdiffの部分にますます宿るようになっているわけだ。そして上の例でもわかる通り、だんだんその分離ができるようになってきた。
絵画はすでに、上のジャクソン・ポロックやイヴ・クラインやマーク・ロスコみたいな、何かを描く技法から離れてその技法や色彩のあり方だけが独立するような世界が成立している。
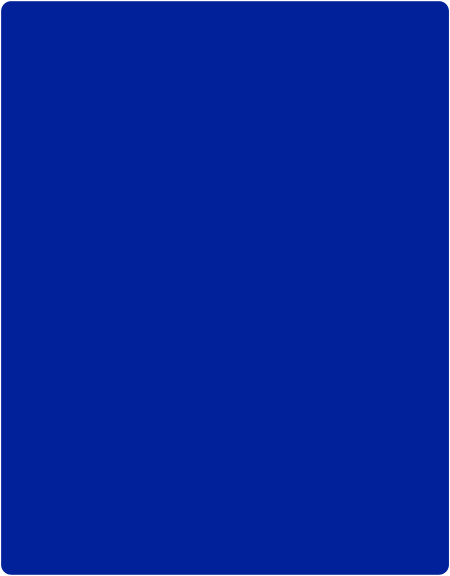
バイクなら、電動バイクのセッティングによりそのdiffだけ取り出せるようになる。自動車ではすでに、自動車のエンジン音を懐かしんで、一部の電気自動車は録音したエンジン音を鳴らしたりできる。それ以外の「余計な」部分を実装するソフトも出てくる。サスペンションもソフトで調整できるし、ステアリングの特性だってソフトウェアで実装できる。そのうち、車の動く部分は完全にプラットフォームとして共通化され、その差分を司るソフトウェアだけが車の価値を決めるような状況すらあり得るだろう。
今にして思えば、パトリシア・ピッチニーニはぼくが認識していたよりずっと鋭かったな、と思う。彼女にはカー・ナゲットという作品シリーズがある。車から、「速そうに見える車の要素だけ取り出す」という変なシリーズだ。

これってまさに、車の「走って移動する」という零度的な機能の部分から、車の価値を生み出すdiffを抜こうという作品ではあるわけだ。
今後、こうしたdiff部分だけを取り出して「価値」を分離できるようになったら、いろいろおもしろい発展になる。ソフトとハードのアンバンドリングは、コンピュータの歴史においてきわめて重要なできごとだった。それがいろんな形で展開する余地が今後出てくる。さっき述べたように、自動車づくりというのはもはや、エンジン設計だの足回りの物理的な構築だのとは無縁の、電気自動車プラットフォーム上にのせるソフトウェアになるかもしれない。機能の中心的な部分とはまったく離れたところでいじるのが価値になるのかもしれない。
その一方で、それがどこまでできるか、というのはまた課題ではある。一部のバカな現代芸術が誤解しているように、ずれればいいってもんではない。めちゃくちゃやって、それでオッケーというわけでもない。ズレの絶対量の大きさで価値が出るわけでもない。うちの子供のつたない楽器演奏が(少なくとも親には) 愛おしくて価値が感じられるのは、それが頑張って「正しい」ものに近づけようとしていて、それでもずれてしまっているからだ。それは意図的にずらしているわけではないんだけれど、でもその人にしかできないズレだ。他のものも、diff部分に価値が宿るからといって、じゃあdiff部分だけあげるからそれだけ享受してね、と言える場合とそうでない場合というのはどうなのか? 一部ではやっている、NFTとかいうバカな話がある。つまらん落書きにNFTつけたら価値があがりました、とかね。たぶんそれは、ここで言っているような話と少し関係はしているんだろう。そしてひょっとしたら、それはこうしたdiffとしての価値の話の、一つの帰結ではある。しょせんdiff部分は、本質的な機能とは何も関係ない、単なるフェティッシュだ。つまらない数字を適当に設定して、それに価値がありますよー、と喧伝してバカがひっかかればいい、というわけね。
その一方で、ぼくは今後、このdiffに宿る価値の根拠というのがもう少しきちんとわかるようになるのではないか、という気がしなくもない。実用から離れた価値なんて、完全に水物で軽佻浮薄な流行りなのかもしれないけれど、でもそうでない部分もあるんじゃないか。なんか、人間の生物学的なあり方と無関係ではない要素が、そうした実用性と離れた価値の何らかの根拠にあるんじゃないか?
一方で、価値というのは無根拠に湧いてくるものだ、とも言える。ちょっと前にはただの雑音だったものが、ジャズやロックとして受け容れられるようになる。ノイズの中から価値が湧き出す——価値があるのだと根拠なしに言い張り、それを自分でも信じ込む能力——それが今後の人間の存在意義になるのだ、という議論も、ぼく自身がよく持ちだしていることでもある。
で、それがどうした? いやどうしたというわけでもない。なんか、どうでもいいことのような気もするし、何か重要になりそうな気もするが、よくわからないので、備忘録的に書いておく。たぶんこれは、世界のバーチャル化と呼ばれるものの一側面なんだろうとは思う。そしてその中で、いまは製造業の一部とされているものが、ますます情報サービス的な産業に変わっていくんだろう。産業構造がかわり、経済の仕組みがかわり、一方で人間の物理的な存在も変わる中で、もっとこういうことを考える必要も出てくるんじゃないか、とは思うんだが。どんなものだろうね。



![エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン [DVD] エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51eaA+vhyRL._SL500_.jpg)