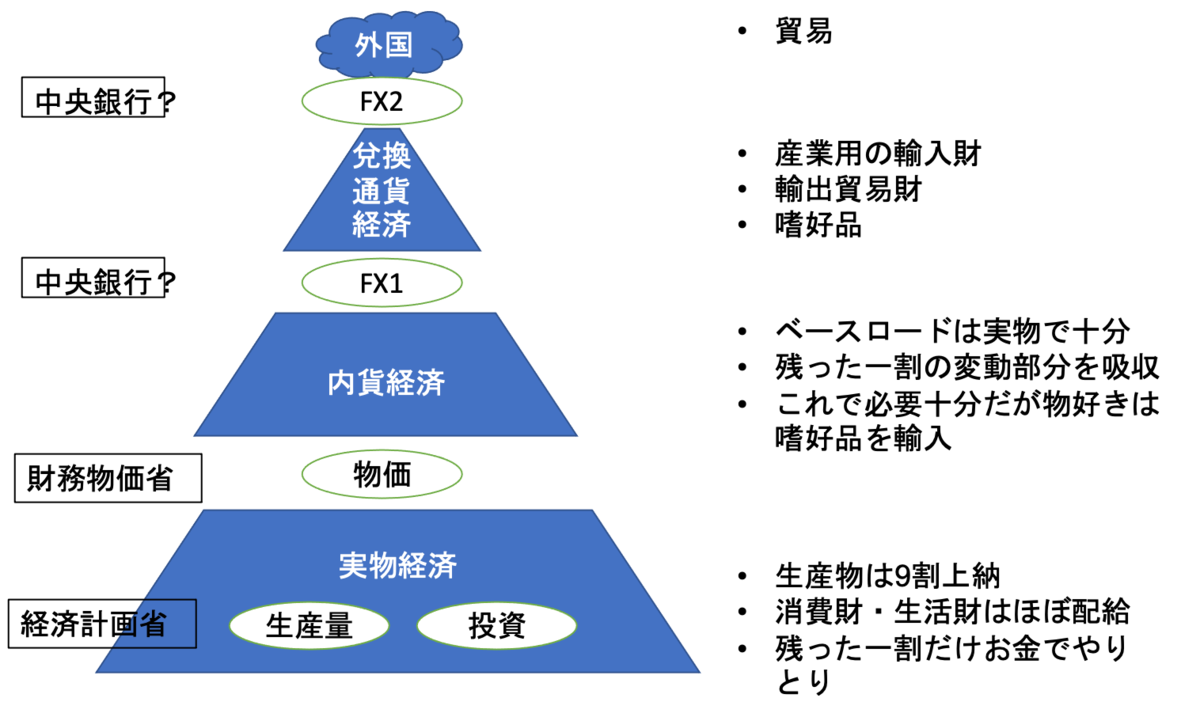Executive Summary
教養というと、実学に関係ないステータス財なのか、それとも実学にも役立つべきベースなのか、みたいな議論が起こる。だがその区別がない場合もあるし、それが理想かもしれないという気もする。大学の上水道学の講義で、屈原の「漁父の辞」に水処理の基本原理が描かれていると、まさに我田引水 (水処理だけに) で強引に読み取ってしまった教授は、なんかそれに近いことをやっていたようにも思う。そこから、直接実学と関係なくても、それと関係あるものを引き出す契機、みたいな教養の捉え方はできないものか?
今日、イベントで教養について話せといわれてあれこれ駄弁ったのですよ。
その中で、教養の役割とかいう話になる。こう、教養というと、実学とは離れた古典知ってます、みたいな、ボリス・ジョンソンがホメロスをギリシャ語で暗唱できますとか、日本なら四書五経だの漢詩だのを暗唱できますとか、もっと最近だとジョイス『ユリシーズ』読んでますとかレンブラント好きですとか、プラトン読んでますとか安藤昌益読みましたとか、なんかのほほーんとした余計な話、みたいな印象はあって、でも最近ではむしろ進化論知ってるとか利己的遺伝子や、意識や知能のモジュール性や、コンピュータ的情報処理にシカゴ学派的な経済学の考え方知ってますとか、そっちのほうかな、とか思う感じもある。
ぼくはなんとなく、まあ「そっち」のほうを重視したい気分はある一方で、実学離れた話もあらまほし、と思ったりもする。考えのベースなのか、あるいはそのベースがあることで存在が許される枝葉なのか、とか。
が、個人的には、その両者がつながる道もあるんじゃないか、という気がしていて、なんかそういうつながりがあると最強だなあ、みたいなことを考えないでもない。
そんなことを考える理由の一つが、大学のときの上下水道学の講義だった。ぼくは全然興味なかったんだけど、必修科目だからしかたない。で、その講義で教授が、開講にあたって己の学問の来歴みたいな、ありがちな話をしていた。そしてそこで、自分が水処理の研究をする中で、屈原の楚辞にある有名な「漁父の辞」を読んで、衝撃を受けてそれが自分の研究に大きな影響を与えたのです、という話をした。
さて読者諸賢は、無教養なサルがほとんどだろうから、漁父の辞の何たるかを知らないでしょう。9割の人は、漁夫の利とまちがえてただろー。実物は以下をみなさい。
そういって見る人はほとんどいないのは知っているので、かいつまんであらすじを。
楚 (というのは秦のライバルの一つ、BC300年頃) に立派で有能で高潔な、屈原という大臣がいて、いろいろ楚の王様にいつもあれこれ正しい提言をしていたのに、王様はバカで言うこときかないし、また他の家臣どもは汚職とおべっかつかいの無能のアンポンタンだらけで、正しいけど面倒なことを言う屈原はやがてうとましがられ、讒言されて、王様にクビにされて追放されてしまうのだ。
で、屈原はもう尾羽打ち枯らしたボロボロの格好で、荒れた川の横を歩き、世の中くさってる、オレだけが清く正しいので追放されちゃったぜ、畜生め、とグチっている。
それを見かけた老漁父が、「何ブーたれてんだよ、世の中が汚いなら少しはそれにあわせろ、空気読めよ、お高くとまってるから追放されちゃうんだよ」と諫める。
屈原答えて曰く「なんでおれがバカで薄汚い他人にあわせなきゃいかんのだ、オレが汚れるだろが。死んだ方がマシだ」
すると漁師あざ笑い「水がキレイなら顔 (正確には冠の紐)を洗えばいい。でも水が汚いなら足を洗えばいいじゃん」とだけ詠んで立ち去りましたとさ。
漁父莞爾而笑、鼓枻而去。乃歌曰、
滄浪之水清兮 可以濯吾纓
滄浪之水濁兮 可以濯吾足遂去、不復与言。
まあ、どんなものにも使いようもあればやりようもあるのに、甘いよアンタ、ということですな。
さてこれを聞いて当然ぼくは、「ああ、どうせ何か、迫害されても正しい信念を持ち続けねばならないとかなんとか、そんな説教くさい話をするんだろうなあ、はやく終わんねえかな」と思っていた。
そして教授曰く
わたしはこれを読んで、頭を殴られるような衝撃を受けた! というのも、ここにこそわが学問の本質の一つが端的に描かれているからです!
はいはい、きましたねー。手短にたのんますよ〜。
ところが、その後にきたのはまったく予想を裏切る話だった。
この漁父の言葉。水がきれいなら顔を洗え。水が汚ければ、足を洗え。つまり、汚い水でも、もっと汚いものを洗うのに使える。これが水処理の本質です! なんでも無理に飲める水準まで浄化する必要はない!むしろ汚い水でもそれにあわせた用途に使うことで、有効利用ができる! 水の再処理、中水利用 、その他あらゆる場面で、基準と用途にあわせた浄水手法が求められる! 上水道学の基本思想がここに描かれているのです!!!
ぽかーん。
いやそれちがうから! 描かれてませんから! それはあくまで例えだから! いや、まあ描かれてはいるけど、ネタにマジレスっつーか (という表現は当時なかったが) 先生、あんた、どういう古典漢文の読み方してるんですか! まさか屈原も、2300年の時を経て自分が水処理のネタにされるとは思ってもいなかっただろうよ!
が、外野が何と言おうとこの先生は、漢文読んで、まさに水処理の原理を感得してしまったわけだし、確かにその通りのこと書いてあるし、うーん。これって、あくまで余計な非実学的な知識たる漢文がまさにまともな工学原理につながってしまったわけで、するとこの先生にとって漢文って、教養ではあるけどどういうもんなのよ、というのはいちがいには言えなくて……
もちろん、だからみんな漢文を勉強しなさい、現代の工学につながる原理が出ております、なんてことはもちろん言えないんだけど、でも「何の役にもたたない漢文、古文」とかいう話がでてくるたびに、ぼくはこの40年近く前の話を想いだしたりするわけです。いやあ、意外と役にたっちゃったりするみたいですよ。なんか、ここに教養というものを考えるうえでのヒントがあるような気が……いや、ないか。
(でも、ちょっとはあると思う。アルキメデスがユリイカしたとき、「だから風呂桶重要です、イノベーションのために風呂環境充実させましょう」といったらアホだし、ニュートンのリンゴ話で、じゃあ物理学発展のためにリンゴの木をもっと植えろというやつは何かかんちがいしていて、彼らがそうしたヒントからあるアイデアにとびついたのは、その人たちがそれをずっと考えていて、それが出てくる契機がたまたまそこにあった、という話。それはこの屈原から上水道の原理を引き出した先生も同じで、たぶん風呂桶やリンゴや屈原である必然性はなかったんだけど、でも何かは必要だった。そうした契機となるいろんなものがまわりにある状況、みたいなものは考えてもいいのかな、とは思うんだ。すると環境の多様性とかそんな話につながるとは思う)
付記:ウヒヒヒ、漁父を漁夫とまちがえてたぜ、付け焼き刃教養がバレますな。


![マッドマックス 怒りのデス・ロード [Blu-ray] マッドマックス 怒りのデス・ロード [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61r1QvHXAfL._SL500_.jpg)




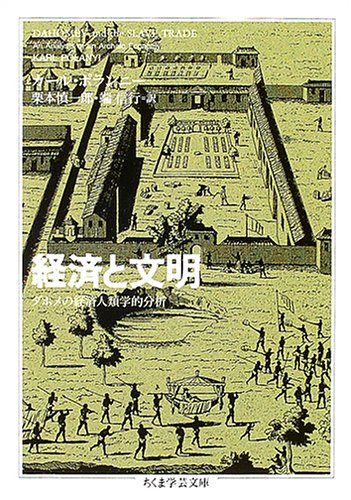
![[新訳]大転換 [新訳]大転換](https://m.media-amazon.com/images/I/41z17W-IFKL._SL500_.jpg)