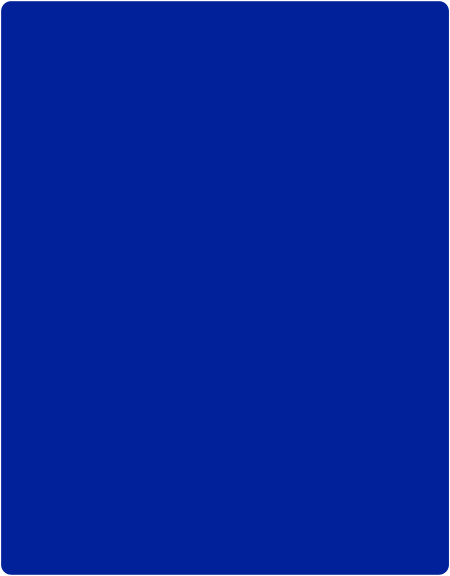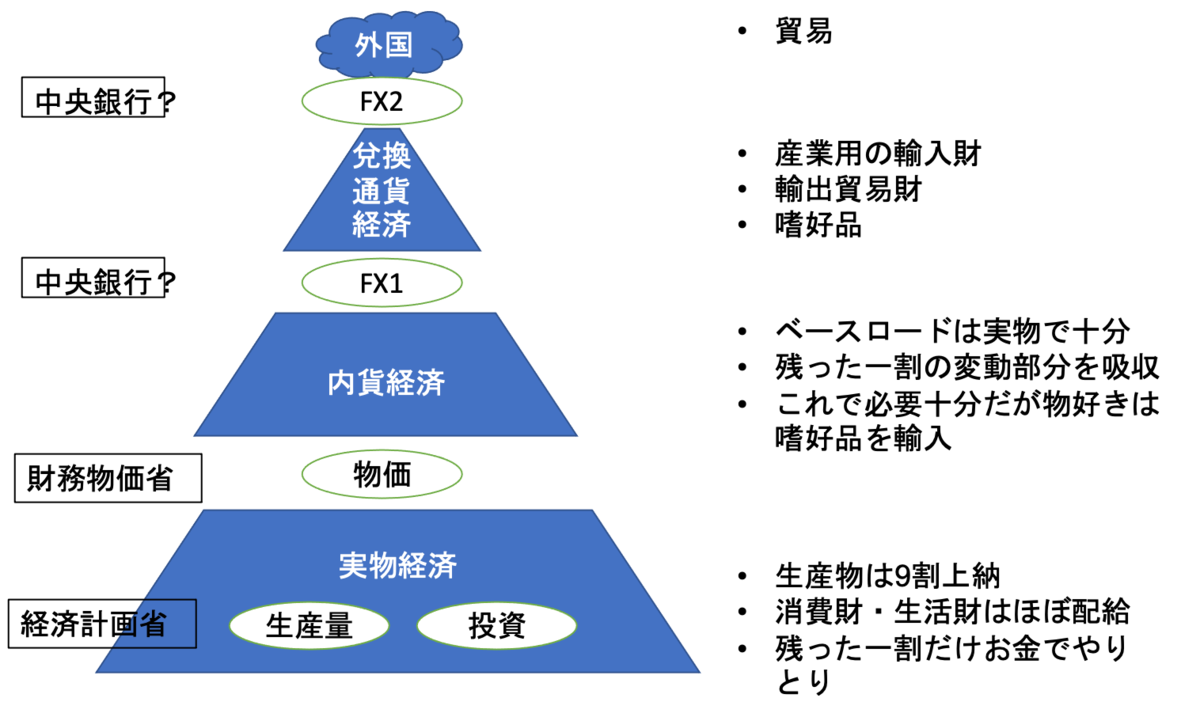Executive Summary
ラフィ『カストロ』(原書房、2017) は、2021年時点で日本で出ている最新のカストロ伝。他の伝記が公式プロパガンダの羅列にとどまるのに対し、カストロに対するきわめて批判的な視点を元に、一般人がカストロの生涯を見て疑問に思う、革命への参入動機、少人数なのになぜ勝利できたのか、その後もなぜ権力が続いたか、ソ連の工作の影響などについて、明解な視点と説得力ある記述を行っている。
米ソ関係とその中のキューバ の位置づけ、という視点しかない他の伝記に比べ、南米におけるコミンテルンのオルグ活動、兄弟の戦略的な役割分担、政権を取ってからの壮絶な粛清と政敵弾圧の記述は圧巻。また文化的弾圧、人間関係、政策評価など他の伝記で無視されている内容にも、詳細な分析が行われる。
批判的なその論旨に賛成だろうと反対だろうと、議論の基盤として使える情報と論理があり、読者が自分の立ち位置を見極める意味でも参考になる。
はじめに
カストロのきちんとした伝記は、意外に少ない。「カストロ」で検索すると、たくさん出てくるけれど、多くはカストロ自身の演説集だったり、自分で語った我田引水の伝記だったりする。また日本人が書いているものの多くは、完全にカストロ/ゲバラのキューバ神話に丸め込まれている心酔者の単なるビリーバー本。公式プロパガンダを一歩も出るものではない。
で、第三者的な立場の人間が、ある程度は客観性をもって書いたと思っていい伝記は、日本語ではコルトマンのやつと中公新書のやつ、そして今回紹介する、このラフィのものだけ、といっていい。英語圏ではあるのかもしれないね。そっちは今後、調べがついたら加筆しよう。
そしてこの中で、まともな独自取材があり、本当の意味で伝記と呼べるのは、このラフィのものだけだ。
明確な視点と当然の疑問への答
カストロとその人生を見ると、まあ当然わいてくる疑問がいくつかある。でも他の伝記はそういう疑問に全然答えてくれない。カストロは何やらどこかで社会正義に目覚め、あとは一心にそれを追求し続け、米ソのパワーゲームの中で涙をのんで妥協を強いられたこともあるけれど、常に独自の声をあげて〜みたいな話になっている。
が。
そんな単純な話はないだろうし、情熱とひたむきさだけでやっていけるほど、世の中は甘くないということくらいみんな知っているはずだ。成功するには成功のための環境なり状況があるはずだ。本書はそれをきちんと考えている。そしてカストロについて、独自の (非常に批判的な) 視点を持ち、その視点がだれしもカストロについて思う、当然の疑問について答を出すにあたり、かなり説得力のある記述をもたらしている。
そもそもなぜ政治に深入り?
まずみんな知りたいのは、なぜカストロがそもそも政治の世界に深入りしたか、という話だ。家族その他の受けた苦境や弾圧を見て怒りに燃えたのか? もともと正義感が強く人の不幸を見過ごせなかったのか? 全然ちがうようだ。
基本的に、フィデル・カストロは子供時代から自分がいちばん目立ってスポットライトを浴びないと気が済まない人物だった。そのためには競合を陥れ、追いやり、殺すことも厭わなかった。幼い頃から、フィデルは学校でのけんかで負けると家から拳銃持ってきて相手を殺そうとするほどのサイコパスだったのだ (これは他の伝記にも書かれている)。
そしてそれまではまったく政治的な関心がなかったのに、大学に入っていきなり政治活動を始めたのは、当時のハバナ大学が大学紛争華やかなりし頃で、それが注目を集めるための最も手っ取り早い方法だったから (それとバスケットボール)。それが次第に先鋭化してテロ活動になり、セクト紛争で他セクトを陥れたり、自分より有力な活動家を密告したりして足場を築く。そして結婚して、新婚旅行でニューヨークにでかけて、謎の三ヶ月間を過ごしたあとで帰国、さらに先鋭化してテロ革命活動に走る。
この三ヶ月間については記録がまったくない。
なぜ彼の運動は勝てたのか?
彼の革命への道は基本的に欺瞞にもとづくものだった。自分はずっと反共、あるいは少なくとも共産主義ではない、だから自分の活動も共産主義的なものではない、と訴え続けるけれど、でもその裏で弟のラウル・カストロは、ずっと共産主義系の連中をオルグして手懐けている。これにより、親米で強権的だったバティスタ政権には反対だが社会主義・共産主義なんかごめんだ、と思っている連中を取り込みつつ、実質は共産主義テロ集団という活動が可能になった。
このため、彼はキューバから逃げ出してメキシコに赴き、そこでオルグと軍事教練を受け、チェ・ゲバラと出会い、グランマ号での決死の帰国をとげて、短期間にキューバ革命を実現する。
そのキューバ革命の一つの不思議は、なぜ百人に満たないカストロ勢力(M26グループ) が、短期間にキューバを制圧できたのか、というもの。本書はそれについて、次のポイントを上げる。
西洋メディアの利用。カストロはメディア戦術がうまく、やたらに目立つ声明やマスコミ発表で耳目を集めた。バカな欧米のマスコミはそれを見て、カストロが反バティスタ政権の旗手だと思いこみ、さらに山にこもって何もしていなかったカストロ勢を、毛沢東の再来まがいにまつりあげた。ちなみに、この手口は毛沢東とまったく同じ。毛もスメドレーやスノーなどのバカなジャーナリストを手先にして、井崗山で取材させて己の存在感を増した。
他の反バティスタ勢力の手柄横取り。キューバでは他の反バティスタ勢力も動いていて、かなり有力なものもあったが、バティスタ軍の対応でつぶされていった。それをカストロ勢はかすめとっていった。中には、それを狙ってバティスタ側に密告したとおぼしき事例もちらほら。
バティスタの敵失を含む幸運。バティスタ軍の士気が低かったのは事実。多くの兵は祖国防衛とかどうでもよかった。また本当ならバティスタ軍につぶされていたはずが、たまたま嵐がきて逃げられたとか、その他ラッキーな出来事も多い。そしてもともと、キューバを東西に分断して地方部をおさえて長期戦にするか東キューバ独立運動でもやるつもりだったのが、バティスタがいちはやく逃げ出してしまい、その空白をあっさり乗っ取った。
もちろん、これはカストロが無能だったということではない。むしろ、機を見るに敏で、非常に有能だったことを示すものだ。人数少ないからヒット&ランに徹するのも賢明。また、キューバに留まっていた部下、特にセリア・サンチェスのオルグ能力は凄かった模様。一方で、彼が単に高潔な理想を掲げて人民の支持を地道に獲得し、という形で革命を実現したわけではないのも事実。
なぜ彼は権力を維持できたのか?
これも多くの提灯持ち本だと、常に揺らぐことなく己の姿勢を維持し続け、人民がそれを支持し続けたからだ、ということになる。確かに人民の支持は強かった。これは事実。でも姿勢が揺らがなかったというのは、まったくのウソだ。
彼は外向きにも内向きにも失策ばかりで、そのたびに方針をコロコロ変えている。その最たるものが、もともと自分もキューバ革命も共産主義ではないと強弁し、それで支持を集めておきながらいきなり社会主義に転換したことだ。
でも、彼らはあるとき仮面をかなぐり捨てて一気に共産主義化を進めた。どうやったか? 対外的には、何でもアメリカのせいにすること。そして対内的には、責任転嫁と情け容赦ない粛清だ。
社会主義化の場合、それはまずアメリカがよくない、ソ連こそ人民の味方と強弁する。そしてどんどん社会主義者や共産主義者を要職につける。そしてそれに対して話がちがうと声をあげたら、その連中はアメリカの手先ということにされる。そしてそことつながりのある人物は、政治的、あるいは物理的に生命を断たれる。革命の三偉人の一人カミロ・シエンフエゴスの死、同じく革命の重鎮ウベル・マトスの粛清、そしてそれに続くかつてのM26グループの要人たちやその派閥の更迭、粛清、謎の死、解体の連続は、まさにそうしたキューバ版の大粛清だった。
この本は、カミロ・シエンフエゴスがなぜかセスナ飛行機に乗ってなぜか晴天の中でなぜか墜落し、なぜか軽量で水に浮くセスナの残骸が一切見つからず、なぜかそれがその後見世物裁判で粛清されるウベル・マトスとの接触直後で、というのがただの偶然の事故だ、という説は取らない。まずラウル・カストロは、軍のトップとして自分よりカミロ人気が高いのを嫉んでいた。またシエンフエゴスはフィデルの不誠実な共産主義転向に懐疑的だったし、それを公然を批判していたウベル・マトスとも仲がよかった。カストロは、ウベル・マトスの逮捕とその舞台の制圧にわざとシエンフエゴスを派遣する。そしてシエンフエゴスがむしろマトスの主張を聞き入れ、カストロに批判的となると、彼の乗った飛行機にニセの航路指示を出して、配下の戦闘機に撃墜させたのだ、と本書は主張する。もちろん憶測ではなく、そのわずかな生き残り関係者に話を聞いて裏は取っている。もちろん、その後カストロたちは、仰々しい真相究明キャンペーンをやっては見た一方で、主要な関係者はすべて口を封じられ、記録もすべてなくなっているという。
ちなみにコルトマン版『カストロ』で、このシエンフエゴスの死について、カストロの陰謀だという証拠はまったくない、と書いた直後に、非常におさまりが悪い形で怪しいスパイ機撃墜の話が同時期にあったという話を一行追加している。これについて、読んだときにえらく違和感があったんだけれど、いまはわかる。これはコルトマンなりに、自分は事情を知っているというのを匂わせた一文なのね。
その後も、政治的な失敗はすべて、自分の政敵(潜在的な相手も含む) をスケープゴートにしたて、人民裁判にかけて潰してしまう。革命直後の失政は、傀儡大統領に仕立てた人物のせいにして、いきなり粛清する。社会主義化が失敗すると、それを旧共産党系の人間のせいにして粛清する。だいたいは、いきなりカストロが何時間もの大演説をうち、その中でいきなり政敵をやり玉にあげ、怒った人民たちがそいつの家やオフィスを取り巻いて、というのがパターンだ。その後は見せしめ裁判だけれど、それが失敗しそうになると分けのわからない8時間演説とかでごまかす、というのを繰り返すのがカストロの政治技法だ。この伝記は、あらゆる段階、あらゆる失策でそれが展開され。勝ち目のないアンゴラ派兵で疲弊した忠実な将校もそれで潰され、もはやキューバ政権内にまともな人材が残っていない状況が生まれていることまで描き出す。
あともう一つは、アメリカがよかれ悪しかれ、ヘマばかりやったこと。カストロ暗殺計画はことごとく失敗している。侵攻もピッグス湾を筆頭に、やってみたけれど予想外に反撃されたらすぐあきらめるし、好機をあっさり逃がすし、またあるときは「潰すぜ!」とイキっておきながら、その直後には「やっぱ手近に悪者がいると便利」と態度を変え、フロリダの亡命キューバ人社会のご威光で方針をコロコロ変える。これでカストロは何度も、政治的にも身体的にも命拾いして、結果的にカストロ支配がダラダラ続く結果となった。
ソ連社会主義との関わりは?
多くの人は、カストロ兄弟の公式の見解をそのまま受け容れて平然としている。つまり、キューバは頑張って独立したけれどアメリカがいろいろ意地悪して、キューバとしては仕方なしにソ連に接近を図ったのだ、というものだ。
でも実際に見てみると、そんなはずはない。ソ連は最初からキューバ革命につながる糸を引いていた。ラウル・カストロが大学時代に親にだまって東欧にわたり、ソ連の教練を受けたのはその明らかな証拠ではある。
そして本書はそれ以外にも、特に運動の初期においてはソ連のコミンテルン対外テロ工作の力が大きかったとみている。1950年代頃、ソ連は中南米に赤化工作のネットワークを展開していた。もちろんアメリカへの足がかりの意味もあるし、途上国の社会主義化はずっとソ連の基本路線だった。その影響力は、たとえばメキシコに亡命したトロツキーを始末するためのラモン・メルカデルなどに典型的だ。ちなみに彼は、晩年はキューバで暮らしている。パドゥーラ『犬を愛した男』は小説だけれど、そこらへんの事情をよく描いている。
その力はアルゼンチン出身のチェ・ゲバラにも及んでいる。『モーターサイクル・ダイアリーズ』の最後に出てくる謎のソ連人はもちろんその一味だ。ボリビアの共産党の重鎮を務め、その後チェ・ゲバラの過激化にも大きな影響を与えた彼の最初の奥さんイルダ・ガデアもそのネットワークの一員だ (彼女との結婚は、コミンテルンが課した試練か罰ゲームなんじゃないかとすら思える。彼女の書いたゲバラ伝を読んでも、関係や親しさが深まるプロセスが一切ないのだ)。本書は、そこに「カリブネットワーク」という赤色工作員のグループがあったことを指摘する。もちろん最初の刑務所襲撃に失敗してメキシコに逃げたカストロ兄弟たちも、そこに関与していたし、キューバ革命もその強い影響下にあった。
これは本書には書いていないけれど、カストロ兄弟の西側メディアの利用手法は、毛沢東とまったく同じだ。そこに同じ影響力の影を見るのはたやすい。その後の見せしめ裁判、粛清等々の技法もソ連のものとまったく同じ。これらが決して独立のものではなかったのではと思うのは自然なことだと思う。
ちなみに本書は、フィデル・カストロはニューヨークでの新婚旅行で、まったく活動記録がない3ヶ月に注目し、そこでおそらくソ連のオルグと教練を受けたのではないかと見ている。
でもカストロはあまりに常軌を逸しており、おとなしくソ連の傀儡にはならなかった。南米全部に自分の息の掛かった革命を広げて、自分が南米合州国の盟主となることを夢見て、その後はアンゴラ戦争を機にアフリカに勢力を拡大できると思い込んだ。南米についてはソ連と連携していた各国の共産党からも苦情がたくさん入ってソ連の不興を買ったけれど、一方でゲバラの臨終時に書かれたボリビア日記を、ボリビアの大臣が盗み出してキューバに渡したことで、まさにキューバが各国の中枢部に手下を送りこんでいたのがあらわになっている。そしてアンゴラでは、もう外国に兵力を出す気のなかったソ連は、これ幸いとキューバにゲタを預けてしまい、結局カストロは最後に自分の野望のおかげでババをひく——その尻拭いをさせられたのはキューバ国民だ。
周辺領域も抑える目配りの広さ
いまのソ連/コミンテルンの影響についての話にも見られるように、本書はキューバを取り巻く地域全体、世界全体の様々な状況にも目配りしている。そしてキューバについて知られている他の側面や、あまり知られていない話まできちんとカバーしてくれる。
アレナスなどの作家弾圧の背景
キューバというと多くの人が、何やら文学も音楽も盛んで文化的に豊かで自由度も高いと思われている。『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』は、そうしたキューバ文化の奥深さを示した映画だとみんな思われている。
でも、実はそれは一部しか真実ではない。『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』は、きわめて才能豊かで活躍していたミュージシャンたちが、社会主義体制下で自殺寸前まで追い込まれていたという話でもあるのだ。
そしてまた、多くの異様な才能を持つキューバ作家たちが弾圧され、亡命を余儀なくされたというのは、多少なりともラテンアメリカ文学になじみのある人々には常識だ。たぶんいま、最も一般に有名なキューバ作家といえば、レイナルド・アレナスだろう。次いで、カブレラ=インファンテかカルペンティエールだ。カルペンティエールはキューバで大御所として祭り上げられているけれど、他の二人はカストロ体制に弾圧・追放されている。なぜだろう? 自由で開放的で文化花開くはずのキューバで、なぜそんなことが起こるのか?
その事情も、この本にしか出ていない。カストロもゲバラも、社会主義に凝り固まっていて、芸術は人民に奉仕しなくてはいけないと考えていて、さらに二人とも南米人のマチスモを色濃く持っていたので、ハバナの芸術界にゲイが多いのを苦々しく思っていた。で、ある映画の公開禁止を皮切りに、しめつけを強化して関連組織を手下で埋め尽くし、気に食わない作家やアーティストを孤立させ、発表の場をなくす。本当なら国外にも出られなかったかもしれないけれど、幸か不幸かカストロは対米プロパガンダの一環で、自分たちは自由で移民受入を拒んでいるのはアメリカなのだ、というのをときどきアピールしようとして、多くの人が国外に脱出するのを黙認している。カブレラ=インファンテもアレナスも、そういうのに乗じて国外に脱出している。
一方、こうした期間にわたりずっとカストロべったりだった人物が、ガブリエル・ガルシア=マルケスだ。カストロの娘のSOSを受け、キューバ作家たちの窮状も知っている。もちろん彼が政敵に行った各種の陰謀その他も熟知している。それでも彼は常にフィデル・カストロの提灯持ちを続け、キューバがまったく意味も勝算もないアンゴラ派兵をやってみせたときにも、それをヨイショする文章を書いたりしている。
ガルシア=マルケスにとって、キューバはまさに自分の作品世界の縮図だ。恐ろしい独裁者に翻弄される南米の小国。ここはガルシア=マルケスにしてみればリアル・マコンドなのだ、というのが本書の指摘だ。彼はそれに魅了されるしかないし、それを否定することなどできなかった、と。そうなのかもしれない。
バルガス=リョサは一方で、キューバの作家たちや人々の窮状を報されて激怒していた。彼がガルシア=マルケスをぶん殴って袂を分かったのは、奥さんをNTRれたせいだと言われるけれど、このカストロ支持をめぐってのこともあるはず。もう少しリアリズム寄りだったバルガス=リョサは、マコンドを外から見て他人事のように愛でることはできなかったのだ。バルガス=リョサはガルシア=マルケスについて『神殺しの物語』という博士論文/絶賛研究を書いたけれど、結局ガルシア=マルケスは、現実の神を殺すだけの度量はなかったわけだ。バルガス=リョサがこの研究を封印したのもむべなるかな。
各種政策のきちんとした評価
他の伝記などでは、カストロの掲げたサトウキビの高い生産目標が達成できなかったり、工業化が進まなかったりしたのを、「うまく行きませんでした」の一言ですませてしまう。でもそうしたものの多くは、そもそも実態をまったくふまえない、ゲバラやカストロが思いつきや勢いで目標をたて、そのために必要なリソースは与えず、とにかくやる気だけですませ、革命が進めば滅私奉公を厭わない「新しい人間」ができるのだと主張し続けた。この本は、それぞれの政策についてちゃんと、当時としての現実的な相場観、それに対してカストロなどがどういう事情でトンデモな目標値を掲げたのか、そしてそれが失敗に終わったときに、彼がその責任をだれにどういう形でなすりつけ、さらなる粛清に使ったかについて非常にしっかりと描き出す。
ちなみにサトウキビの大増産プロジェクトは、都会人を畑に狩り出して、計画時点ではその連中が熟練労働者並の生産性をたたき出せるという計算で作り上げた、下放と大躍進政策をあわせたような代物。西側メディアの利用手段が毛沢東と似ていたと述べたけれど、この大躍進政策もそっくりとなっている。
そして彼が、ペレストロイカにどう反応したのか (もちろん大反発)、その後の様々な東欧解体やアラブの春に対してもどういうふうに対応したのか、融和的な政策に一瞬流れてからすぐに強硬路線に戻った様子、外貨を求める中で手を染めてきた様々な怪しい活動も描かれている。それを見ると、アメリカによるテロ支援国指定も決して思いつきとは言えないように思えてくる。
人物評価
周辺人物に関する記述もおもしろい。特に弟のラウル・カストロ。通常、ラウルは華々しい兄の影に隠れ、無能で愚鈍な追随者と思われているけれど、実はそれは二人が作り上げた役割分担だ。実際にはラウルのほうが執念深くて権力争いに敏感だったという。
チェ・ゲバラとはものすごくウマが会ったけれど、その最後は感情的にはつながりつつも実利的に処分という非情なもの。他の仲間のように陥れて粛清したわけではないけれど——いや、コンゴやボリビアに送りこんだのはどこまで本人の希望で、どこまでカストロの意図だったのか。でも、ゲバラを政府中枢から遠ざけて周縁的な存在にしようとしたのはまちがいない。
いまのキューバの大統領ディアスカネルが、このカストロ兄弟との関係の中でどういうふうに登場したのかについても、触れているのはこの本だけだ。
また家族との関係も、自分の革命的な活動を正当化するために父親をものすごく悪辣な存在にしたてたとのことで、妹がフィデルに反発しているのはそうした父親をまったくの作り話で捏造しているからだ、という話。女性関係も、コルトマンの伝記ではかする程度の扱いだったマリータ・ローレンツが、愛人で子供まで生まされ、その後CIAに暗殺要員として雇われたのに失敗して、という話をきちんとフォロー。一応伝記なんだから、そういう話はぬかしてはいけないでしょう。
その他ゴシップ
そしてもう一つ、カストロ本人とはまったく関係ないながら興味深いのが、JFK暗殺との関わり。カストロ自身はもちろんそれにまったく関わっていないんだけれど、犯人とされているオズワルドはソ連共産主義マニアで、キューバにも渡ろうとしている。そしてかつてキューバ侵攻やカストロ暗殺に関わって失敗した人々ともやたらに接触がある。マリータ・ローレンツとオズワルドは知り合いだ。どうもJFK暗殺は、カストロ暗殺を仕組んだ連中が、その後立場がなくなったのに焦って、キューバがJFK暗殺を演出したように見せかけることで、アメリカが本気でキューバ侵攻に乗り出すよう仕向けていた可能性がそこそこあるとのこと。もちろん、JFK暗殺が本当にオズワルドの仕業かはアメリカ陰謀論の定番になるほどで決着がまったくついていないのはご承知の通り。でもそんな変なネタが次々に出てきて、読み出すと止まらないのがこの本のいいところだ。
最後に形式面
この本、上下巻で長そうに見えるので敬遠する向きもあるだろう。でも、一段組みで文字も大きい。二段組で字の小さいコルトマン版に比べて、実はそんなに長いわけではない。そしてカバーする内容は、2002年までのコルトマン本に比べて、2015年までだし、現代的な関心にもずっとマッチしている。まずその点だけでも、相対的にラフィ本の方が優位にある (前世紀の中公新書は論外ね)。
書きぶりは、フランス人の書く伝記にありがちな、見てきたような再現ドキュメンタリー風。「そのとき、カストロ少年は愕然とした!」「フィデルとラウルは、怒鳴り合いの末に声も出なくなり、息を荒げたままにらみ合っていた。キューバ革命の未来がその一瞬にかかっていた」みたいな感じ。ぼくも最初、それにひっかかったんだけれど、やがて気にならなくなる。すべて一応調べて裏はあるみたい。最近の欧米の本にありがちな、一言半句に注で出典がつく形にはなっていないけれど、でもおおむねどこから出てきた話かについては、参考文献を見ればわかる。
まとめ
本書は最終的に、オバマの融和政策でキューバの社会主義はもう完全に終わり、骨抜きにされて過去の話になってしまうだろうと予想している。2015年だと、そう思うのも当然のことだ。でも実際には歴史はそうはいかず、2016年にトランプが当選してキューバに対する制裁を一気に逆転強化させてあらゆる面での締め付け/いやがらせをかえって強化させてしまった。おかげでまた1990年代のソ連崩壊直後に匹敵する苦境にキューバは置かれている。そしてソ連の支援がなくなった1990年以来、メンテせずにだましだまし使ってきたインフラ (電力や道路などの物理インフラも、中央集権計画経済という政治経済システムというソフトインフラも) がもはや残存価額もないくらい完全に崩壊してしまい、停電や物資不足や拙速な経済大改革のよる混乱で、政府への抗議デモも起こり、それを弾圧したことで国際的に孤立し、政権の基盤についても楽観視できない状況だ。
たぶん、それはカストロの遺産 (それもあまりよくない遺産) とどうむきあうのか、という判断をキューバに迫るものとなる。表舞台から退いたとはいえ、ラウル・カストロはまだいるし、彼はずっと院政を敷いてきた人だったからあまり状況は変わっていないとすらいえる。あと数年は現状が続くのかもしれない。いずれ彼が他界したとき何が変わるか——あるいは何も変わらないか——が、キューバの未来を大きく左右するのかもしれない。粛清しすぎて人材が枯渇し、有能は人々はすでに大挙して外国に逃げ出してしまったキューバで、これから何ができるのだろうか?
確かに本書はカストロにきわめて批判的な伝記ではある。それだけで本書を敬遠したり否定したりする立場もあるのかもしれないね。その一方で、ここに書かれた話は完全には一蹴できない重要なポイントばかり。カミロ・シエンフエゴスは殺していないかもしれないけれど、かつての同志たちを次々に粛清してきたのは事実。それに対して、それにもかかわらずカストロはすごかった (または、それだからこそカストロはすごかった) と讃える伝記というのがあり得るのか? 単なる公式発表のおさらいにとどまらない、まともな資料と取材に基づいた話ができるのか?
本書に書かれたことがすべて正しいかは、もちろん一読者には判断がつかない。ぼくだって、そんなことは断言できない。こんなの全部でっちあげで、カストロへの悪意が生み出した妄想だという立場もある。でもそれならば、こうした各種の糾弾についての別の解釈とは何なのか、というのは求められる。公式の証拠がない、というだけでは弱いだろう。
一応、伝記を名乗るからには、キューバやカストロ体制について関心のある人が当然考えるであろうポイントについて、何らかの示唆を与えるものであってほしい。なんとなく「いろいろありました。キューバがんばれー」と米ソ冷戦エピソードのおさらいでは、こんな本を読んだ意味がない。カストロをどう評価するのか (そしてなぜ) について、著者なりの見解とその根拠を与えるものであってほしい。それに読者が賛成するかは、また別の問題ではあるけれど、少なくともその読者なりの判断をする材料は提供してほしい。
そして、ぼくがコルトマンの伝記についての評で冒頭に書いたことを見て欲しい。カストロの人生は単線的で、粛清すべき敵もなく云々。でもこれは完全にまちがっていた。ただ彼はそうした部分をうまく表に出さなかっただけだった。この本は、ぼくのカストロ観を改めてくれた。
本書はそれだけの力を持つ、日本語で唯一の伝記だと思う。その意味で、カストロの伝記を読むのであれば、いまの日本ではこれしかないとすら言えそう (まだぼくが未読のやつがあるのかもしれないけど)。



![ブエナ★ビスタ★ソシアル★クラブ Film Telecine Version [DVD] ブエナ★ビスタ★ソシアル★クラブ Film Telecine Version [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51mCyn9ufzL._SL500_.jpg)










![エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン [DVD] エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51eaA+vhyRL._SL500_.jpg)