訳者まえがき
まちがって公開されたとおぼしき、ロシアがウクライナ征服に成功していた場合のロシア国営通信 RIA予定稿の全訳。すぐに引っ込められたが、Wayback Machineにしっかり捕捉されていた。すごい代物。いくらでも言いたいことはあるが、読めば多くの人は同じことを考えるだろうし、ある100年近く前のドイツの人が書いた文章との類似も明らかだとは思う。
以下のツイート経由で存在を知った。ありがとうございます!
1 “The resolution of the Ukraine question.” A mistakenly published Russian article gives us a chilling insight into the neo-imperialist thinking in Russia that drives Putin’s decision to invade Ukraine. A (long) THREAD.
— Thomas de Waal (@Tom_deWaal) February 28, 2022
翻訳ソフトの力を借りて、英語経由で翻訳しました。重訳だがそんな複雑な文ではないので、大きなミスはないと思うがお気づきの点があればご指摘いただければ幸甚。また文中のCTSO、ユーラシア連合、ミュンヘン演説などへのリンクは訳者が勝手に入れたもの。
(あとオリジナルでは写真は関連記事へのリンクになっている。その関連記事の題名を、最初は中見出しで処理していたが、文とずれているので写真のキャプションに入れ込みました)
訳者 山形浩生 hiyori13@alum.mit.edu
ロシアの攻勢と新世界の到来 (2022/02/26)

 ピョートル・アコポフ (Petr Akopov)
ピョートル・アコポフ (Petr Akopov)
目の前で新世界が生まれようとしている。ロシアのウクライナにおける軍事作戦は、新時代をもたらした——しかも同時に三つの側面から。そしてもちろん、四つ目の側面としてロシア国内でも。いまここに、イデオロギー面と、我々の社会経済システムのモデルそのものの両方の面で、新時代が始まる——だがこれについては後で別に語る価値がある。
ロシアはその統一を回復しつつある——1991年の悲劇、我らが歴史上の恐るべき大災厄、その不自然な断絶は克服された。そう、多大なコストはかかり、さらに実質的な内戦という悲しい出来事を経てのことでもあった。というのも、ロシア軍とウクライナ軍に属することで隔てられていた兄弟たちが、いまなおお互いに撃ち合っているからだ。だがいまや反ロシアとしてのウクライナはもはや存在しない。ロシアはその歴史的な完全性を取り戻し、ロシア世界をまとめ、ロシアの人々を一体としている——その大ロシア人、ベラルーシ人、小ロシア人というすべてを。これを放棄してたなら、この一時的な分断が何世紀も続くのを容認していたら、先祖の記憶を裏切ることになるだけではなく、ロシアの大地の解体を許したことで、子孫たちに呪われることになるだろう。

ウラジーミル・プーチンは、ウクライナ問題の解決を将来世代に委ねないと決断したことで、まったく誇張抜きで、歴史的な責任を引き受けた。結局のところ、この問題の解決は常にロシアにとって主要な問題であり続ける——理由は大きく二つある。そして国家安全保障の問題、つまり反ロシアと西側が我々に圧力をかけるための前哨拠点をウクライナから排除するという問題は、その中で二番目の重要性を持つものでしかない。
筆頭の問題は常に、分断された人々のコンプレックス、国民的恥辱のコンプレックスだ。ロシアという家はまずその基礎の一部 (キエフ) を失い、さらに二つの国家として、一つの国民ではなく二つの国民として存在するのを受け容れねばならなくなったのだ。これはつまり自らの歴史を放棄し、「ウクライナだけが真のロシアだ」といったイカレた主張に同意させられたり、あるいは無力に歯がみして、「我々がウクライナを失ったとき」 を思い出させられるということだ。ウクライナを取り戻すこと、つまりロシアの一部に戻すのは、十年ごとにますます困難になる——塗り直し、ロシア人の脱ロシア化、ウクライナの小ロシア人たちをロシア人に刃向かわせる動きが勢いを増すからだ。そして西側がウクライナに対し、全面的な地政的、軍事的支配を掌握してしまえば、そのロシア復帰は完全に不可能となる——大西洋ブロックと戦わねば取り戻せない。

いまやこの問題はなくなった——ウクライナはロシアに戻った。これは別にその国家体制が解体されるということではないが、再編され、再確立されて、ロシア世界の一部という自然な状態に戻るということだ。その範囲内で、どのような形でロシアとの連合がまとめられるのか (CSTO やユーラシア連合を通してか、あるいはロシアベラルーシ連合国か)? これは反ロシアとしてのウクライナの歴史に終止符が打たれた後に決められる。いずれの場合でも、ロシア人民分断の時代は終わりつつある。
そしてここに、きたるべき新時代の第二の側面が始まる——これはロシアの西側との関係をめぐるものだ。ロシアですらない。ロシア世界全体、つまりロシア、ベラルーシ、ウクライナの三国家が、地政的に単一の全体としてふるまうのだ。こうした関係は新しい段階に入った——西側はロシアがヨーロッパとの歴史的な国境に復帰するのを見ている。そしてこれに対して大声で不満を述べているが、魂の奥底では、その西側ですら、それ以外の形があり得ないことを自分に認めざるを得ないのだ。
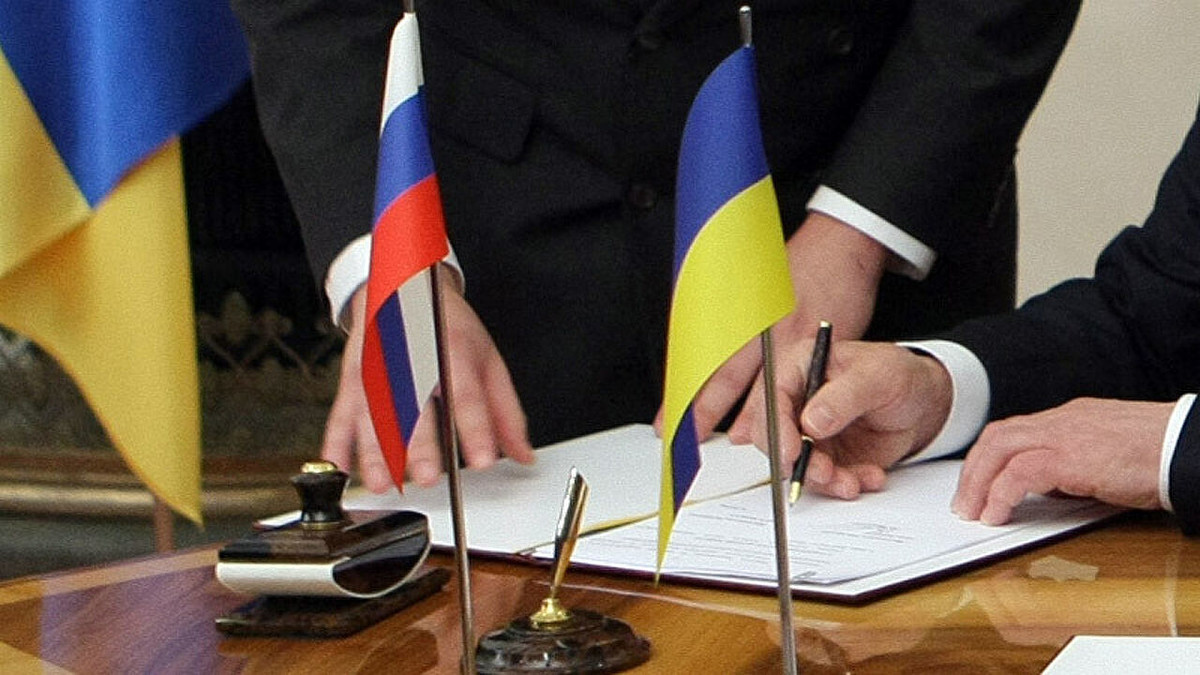
旧ヨーロッパの首都、パリやベルリンのだれであれ、モスクワがキエフをあきらめるなどと本気で信じていたのだろうか? ロシア人たちが永遠に分断された人民であり続けるなどと? しかもそれが、ヨーロッパが統合され、ドイツとフランスのエリートどもがヨーロッパ統合の支配権を、アングロサクソンからもぎとって、統一ヨーロッパをまとめようとしているときに? ヨーロッパ統合が可能になったのは、ドイツが統一できたおかげでしかなく、そのドイツ統一はロシアの善意 (だが賢明なものではなかった) のおかげでしかなかったのだ。それがロシアの大地でも起こるのに不興を抱くのは、恩知らずにもほどがあるだけではなく、地政的な愚行だ。西側全体、まして特にヨーロッパは、ウクライナを影響圏にとどめておくだけの強さを持っていなかったし、ましてウクライナを自分で奪取するだけの強さはなかった。これを理解しないとなると、どうしようもない地政的な愚者と言わざるを得ない。
もっと正確に言えば、選択肢は一つしかなかった。ロシア、つまりはロシア連邦の将来の崩壊に賭けるということだ。だがそれがうまく行かなかったという事実は、20年前にすでにはっきりしていたはずだ。そしてすでに15年前の、プーチンのミュンヘン演説の後では、つんぼですら聞こえたはずだ——ロシアは復活しつつあるのだ、と。

いまや西側は、ロシアが戻ったという事実のため、ロシアを犠牲にして儲けようという計画を正当化しなかったため、西側の領土を東に拡大するのを容認しなかったために、ロシアを罰しようとしている。我々を罰しようとするにあたり、西側は自分たちとの関係がロシアにとって決定的な重要性を持つのだと考えている。だがもうとっくの昔にそんな状況ではなくなっていた——世界は変わったのだし、これはヨーロッパ人だけでなく、西側を支配するアングロサクソン人たちもよくわかっていることだ。ロシアに西側がどれだけ圧力をかけても、何も起きない。双方には、対立の昇華に伴う損失が生じるが、ロシアは道徳的にも地政的にもそれに耐える用意がある。だが当の西側にとって、対立の高まりは巨大なコストがかかる——しかも、その主要なコストはまるで経済的なものではないのだ。
ヨーロッパは、西側の一部として、自立を求めた——ドイツによるヨーロッパ統合の活動は、アングロサクソンがイデオロギー的にも、軍事的にも、地政的にも旧世界を統制している状況では筋が通らない。そう、そしてそれは成功することもできない。というのもアングロサクソン人たちは、統制されたヨーロッパを必要としているからだ。だがヨーロッパは、別の理由からも自立性を必要としている——アメリカが孤立主義に入ったり (これは高まる国内の紛争や矛盾の結果だ) あるいは地政的な重心が移行しつつある太平洋地域に注目するようになったりしかねないからだ。

だがロシアとの対決は、アングロサクソン人たちがヨーロッパをひきずりこもうとしているものだが、ヨーロッパ人から独立の可能性すら奪ってしまうものだ——ましてそれが、ヨーロッパが中国と決別しようとしているのと同じやり方だというのは言うまでもない。もしいまや「ロシアの脅威」のおかげで西側ブロックがまとまるため、大西洋の英米人どもが喜んでいるなら、ベルリンとパリは、自立の希望を失ったおかげで、ヨーロッパプロジェクトは中期的にあっさり崩壊するというのを嫌でもわかるはずだ。だからこそ独立精神のあるヨーロッパ人はいまや、東部国境に新たな鉄のカーテンを構築するのにまったく興味がないのだ。それがヨーロッパにとっては座礁の岩場になると認識しているからだ。世界指導者としてのヨーロッパの世紀 (もっと正確には5世紀) はどのみち終わる——だがその将来に向けて様々な選択肢はまだ可能なのだ。
新世界秩序の構築——そしてこれは現在の出来事が持つ第三の側面だ——は加速しつつあり、その輪郭はアングロサクソン的グローバリゼーションの覆いを通じて、ますますはっきり見て取れるようになりつつある。多極世界がついに現実となった——ウクライナでの軍事作戦を実施しても、西側以外のだれもロシアに敵対するに到っていない。というのも、その他の世界はこれを見て完璧にわかっているからだ——これはロシアと西側との紛争であり、これは大西洋英米人どもの地政的拡張への反応であり、これはロシアが世界における歴史的な空間と場所への復帰なのだ、と。

中国、インド、ラテンアメリカ、アフリカ、イスラム世界、東南アジア——だれも西側が世界秩序を率いているとは信じていないし、まして西側がゲームの規則を決めるなどとは考えていない。ロシアは西側に挑戦しただけでなく、西側のグローバル支配の時代が、完全かつようやく終わったと考えてよいのだということを示したのである。新しい世界は、あらゆる文明とあらゆる権力中枢によって構築され、もちろんそれは西側 (統一されているかは知らないが) と一緒に行うこととなる——だが西側の条件に従ったものにはならないし、西側がそのルールを決めることにもならないのだ。
原文は以下。
Wayback MachineがロシアRIAのサイトから拾っているし、訳者は本物だと思っている。Archive.orgに過去10年以上にわたり毎月少額とはいえ寄付を続けた甲斐があったぜ!
さらにウズベキスタンのスプートニクのサイトには、まだそのまま堂々と載っている。おそらく本物。
またパキスタンのメディアには英訳版が載っている。ただしこれ、途中でWestがW-estなったままのところや「ti-mes when “we lost Ukra-ine.”」という変なハイフンの入り方とか、メディアとして正式な記事を渡してもらったのか、翻訳ソフト丸投げかなんかの加工なのかちょっと不明。
https://thefrontierpost.com/the-new-world-order/thefrontierpost.com
また、こちらにも別の全訳あり。
誤って公開された露国営通信記事がプーチンを理解するのに有用だと思ったので全訳した。
— ブーバチカ (@Lechka_ru) March 1, 2022
「大ロシア、小ロシア、白ロシアの集結を放棄し、一時的な分離の固定化を許してしまったらロシアの土地の崩壊を許したことによって祖先の記憶を裏切るのみならず子孫からも呪われる https://t.co/oGK1dw5bxv
もちろんクリエイティブコモンズなので、いちいち断らず好きに使ってください。原著の人が著作権とか主張するかな〜。でも、いまやもちろんこんなの出したって認めるわけにはいかないと思うんだ。
 この作品のライセンスはCreative Commons Attribution 4.0 International License. 出所を明記すれば転用、商業利用なんでも可能。
この作品のライセンスはCreative Commons Attribution 4.0 International License. 出所を明記すれば転用、商業利用なんでも可能。















